COLUMN

運動指導の「気付き」の瞬間|Michael Boyle氏寄稿
日々新たなトレーニング理論が増えていく中で、インプットした内容を日常のクライアント指導にどう活かせばよいのか悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本コラムでは、最新のトレーニング理論やそれを現場に活用するために必要な器具をご紹介します。ぜひ、日常の指導にお役立ていただけますと幸いです。 今回は Mike Boyle Strength & Conditioning(MBSC)の創設Michael BoyleがPERFORM BETTER本社のブランドサイトに寄稿した「Mike Boyle's "Ah-Ha" Moments」をご紹介します。 トップアスリートのトレーニング指導者としてはもちろん、民間のトレーニング施設としても成功を収めているMBSCの創業者としても活躍中のMike Boyleコラムをぜひ最後までご一読ください。 マイク・ボイルの「Ah-Ha(気づき)の瞬間」 私の親友であるアルウィン・コスグローブは、「Cosgrove’s Five Ah-Ha! Moments: The Education of a Misguided Trainer」という記事を書きました。アルウィンは様々な面で私にインスピレーションを与えてくれます。多くの場合、それは彼が二度がんを克服したという人生経験から来るものです。しかし今回は、彼の文章そのものから大きな刺激を受けました。 以下は、リハビリ、トレーニング、栄養に関する私自身の「Ah-Ha(気づき)」の瞬間の数々です。これまでの常識を覆されるかもしれません。 まず最初に、あなたがまだ聞いたことのない最も賢い人物を簡単に紹介します。これまでビル・ハートマンがその称号を持っていたと言われていましたが、今や多くの人が彼の卓越性を知っています。私が今回「世に知られていない天才」と推薦したいのは、理学療法士の Dr. Dan...
運動指導の「気付き」の瞬間|Michael Boyle氏寄稿

TUSS(不安定な接地面上でのトレーニング)|近藤 拓人先生|ウェビナーレポート
今回は、先日開催した近藤拓人先生による無料ウェビナー「TUSS(不安定な接地面上でのトレーニング)の活用法」の内容の一部をご紹介します。 TUSSの理論的背景と実践的な活用方法について解説いただきました。 不安定面での運動がもたらす神経筋への影響や、目的に応じた効果的な導入のポイントを整理し、現場ですぐに活かせる内容となりました。 ■テーマ:TUSS(不安定な接地面上でのトレーニング)の活用法 ■開催日:2026年1月24日 ■講師:近藤 拓人 氏(AZCARE代表/NEXPORT代表) TUSSとは? TUSS(Training on Unstable Surface)とは、BOSUやバランスディスクなど不安定な接地面上で行うトレーニングの総称です。 近年は「不安定だから良い」ではなく、「不安定性をどのように活用するか」という目的意識が重要とされています。 この考え方は、神経筋制御や感覚統合の理解にも直結しており、姿勢・動作の再学習の一環として位置づけられます。 現場では、リハビリからアスリートへの感覚の再教育まで幅広く応用されており、目的の明確化が最も重要なポイントとなります。 メリット 1.筋活動の増大 不安定面上では姿勢保持に関わる深層筋の活動が増し、局所的な筋活動が増大する。 姿勢安定を目的としたトレーニングとして有効です。 ただし、力を発揮するトレーニングではなく、姿勢を保ちながら協調的に動く練習として捉える必要があります。 2.固有受容感覚の強化 不安定面での運動は、関節内の固有受容感覚を賦活させる効果があります。 慢性足関節不安定症のリハビリなどで有効とされています。 不安定性の程度を段階的に設定することで、末梢からの感覚入力を安全に高めることができます。 3.運動連鎖の促進 不安定環境では体幹と四肢が協調して働くため、運動連鎖を促進する効果があります。 特に姿勢制御や動作学習に応用できます。 スポーツ現場では、全身の連動を意識づける“プレトレーニング”として導入されるケースも多いです。 デメリット 1.特異性の原則...
TUSS(不安定な接地面上でのトレーニング)|近藤 拓人先生|ウェビナーレポート

アスリートにおける腰痛(根城 祐介先生)|ウェビナーレポート
今回は、先日開催した根城 祐介先生による無料ウェビナー「アスリートにおける腰痛」の内容の一部をご紹介します。 競技現場で多くみられる非特異性腰痛をテーマに評価・分析・エクササイズの実際を通してアプローチの考え方を解説いただきました。 ■テーマ:アスリートにおける腰痛 ■開催日:2026年1月20日 ■講師:根城 祐介 (Active-Aid Program 代表) 非特異性腰痛の特徴 腰痛の約8割を占めるといわれる「非特異性腰痛」は、レントゲンやMRIなどの画像診断で原因が特定できないタイプの腰痛を指します。 構造的な損傷だけでなく、動作・姿勢・負荷のかかり方・可動性のアンバランスといった複合的な要因が重なって生じるケースが多いです。 アメフト選手を対象にした調査では、約3割が腰痛を抱えており、シーズンを棒に振る選手も少なくありません。 全競技の怪我のうち約10〜15%が腰痛関連であり、繰り返し動作や過度な姿勢保持が大きなリスク因子となっています。 腰痛リスクを高める動作として「屈曲」「回旋」「不良姿勢での反復」が挙げられ、競技種目に限らず、日々の動作や負荷の蓄積が負担となっているかを観察する姿勢が求められます。 動作分析 アスリートの腰痛は、運動時間・強度・特異的動作の3点が一般的なケースと大きく異なります。 高強度で非日常的な動きを繰り返すことで、腰部へのせん断ストレスが増し、股関節・体幹・胸郭の連動性が崩れることが痛みの要因になります。 股関節のモビリティが低下すると、体幹が代償的に動いてしまい、結果的に腰部へ過剰なストレスが集中します。 股関節と体幹の協調を欠いた瞬間に“画像には映らない腰痛”が起こるという考え方は、腰痛を「構造的損傷」ではなく「動作の破綻」として捉える重要な視点となります。さらに、体幹と骨盤の位置関係が崩れると、力の伝達効率や軸回旋も乱れ、パフォーマンス低下や慢性的な負荷の蓄積につながります。 ニュートラルポジションの維持が腰部保護とパフォーマンス両立の鍵になります。 エクササイズ 腰痛の改善や再発予防においては、体幹のスタビリティと胸郭のモビリティを中心に再教育することが重要です。 股関節の働きを引き出すためには、その上位構造である体幹・胸郭の機能を整える必要があります。 体幹スタビリティエクササイズ(三ヶ月ポジション) レバーベルを使用し先端に負荷をかけた状態で叩く動作を行うことで、腹圧を保ちながら上肢を動かす。 ミニバンドを膝に装着し股関節外転を加えることで、フィードフォワード型の安定性が高まり、体幹と下肢の協調が促されます。 胸郭モビリティエクササイズ 片手で支え、もう一方の手でスライドさせながら胸郭の回旋と伸展を引き出す動作です。 バルスライドを使うことで、物体を操作しながら自分の身体を制御する感覚を養うことができます。...
アスリートにおける腰痛(根城 祐介先生)|ウェビナーレポート

なぜケトルベルを活用するのか?|Don Saladino氏寄稿
日々新たなトレーニング理論が増えていく中で、インプットした内容を日常のクライアント指導にどう活かせばよいのか悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本コラムでは、最新のトレーニング理論やそれを現場に活用するために必要な器具をご紹介します。ぜひ、日常の指導にお役立ていただけますと幸いです。 今回は The Elite Trainer’s Perspective Don SaladinoがPERFORM BETTER本社のブランドサイトに寄稿した「Why The Kettlebell?(なぜケトルベルなのか?)」をご紹介します。既に多くの施設やチーム、個人に導入いただいているケトルベルの利便性や活用についての考え方を紹介しておりますのでぜひ最後までご一読ください。 なぜケトルベルなのか? トレーナーの視点から見た“最強のトレーニングツール”(原題:Why the Kettlebell? — Don Saladino & Christopher Holder) フィットネスの世界には、さまざまな器具やツールがあります。マシン、ダンベル、バーベル、あるいは最新のトレーニングガジェットまで選択肢は数え切れません。その中で、なぜケトルベルはトップトレーナーたちに選ばれ続けているのでしょうか? トップトレーナーがケトルベルを選ぶ理由 ニューヨークを拠点に活躍する著名パーソナルトレーナー、ドン・サラディーノはこう語ります。 「私のクライアントには、映画撮影を控えた俳優も多くいます。怪我をせずに高いパフォーマンスを発揮し、なおかつ“見た目”も周囲から求められるレベルに仕上げなければならない。そんなハリウッド俳優の身体づくりにも、ケトルベルは最適なんです。」 彼がケトルベルを「最も動的で、有効性の高いトレーニングツール」と評価する理由は、大きく分けて次の3つです。 1. 1つのツールで5つのトレーニング要素をカバー ケトルベルトレーニングは、...
なぜケトルベルを活用するのか?|Don Saladino氏寄稿

Q&Aに回答|ヒップロックを徹底解説!(九鬼 靖太先生)|ウェビナーレポート
今回は、昨年末に開催した九鬼靖太先生による無料ウェビナー「Contextual Strength Training の基礎と応用 -ヒップロックの徹底解説-」の内容の一部をご紹介します。 先日の公開したレポートではCST理論とヒップロックのメカニズム、エクササイズを中心にお届けしました。 今回は、ウェビナー後半に行われたQ&Aセッションより、参加者から寄せられた質問と九鬼先生の回答を抜粋してお届けします。 ■テーマ:Contextual Strength Training の基礎と応用 -ヒップロックの徹底解説- ■開催日:2025年12月28日 ■講師:九鬼 靖太 (大阪経済大学 人間科学部 准教授、CST講師) Q1.九鬼先生は基礎的筋力トレーニングの指導はされますか?また、S&Cコーチに文脈的筋力トレーニングの理解を求めますか? A: もちろん私も基礎的筋力トレーニングもやります。 筋力やパワーといった身体リソースがなければ、パフォーマンスの向上はあり得ません。 一方で、それだけでは競技動作には直結しない。 だからこそ、基礎的筋力をしっかり持った上で「文脈的なトレーニング」で橋渡しをする必要があります。 S&CコーチにはCSTの考え方を理解してもらえるとありがたいですね。 「ベースを上げてくれているから、次はこういう動きに発展できる」と共有しやすくなります。 Q2.ヒップロックをエクササイズとして行うと“ヒップロックが上手くなる”と思いますが、その結果、基礎的筋力トレーニングの効果を競技動作に活かせるという理解で合っていますか?また、これはCST全体にも当てはまりますか? A: はい、その理解で大丈夫です。 ただ、ヒップロックという形を作ることに意味があるのではなくて、腰部を側屈する力が出るというところがすごく重要です。 ヒップロック動作を通して骨盤が動くようになると、基礎的な筋力で得た力を競技動作に「転写」できるようになります。 CST全体で考えても同じで、筋力を“どう使うか”を学ぶことが目的です。...
Q&Aに回答|ヒップロックを徹底解説!(九鬼 靖太先生)|ウェビナーレポート

ヒップロックを徹底解説!(九鬼 靖太先生)|ウェビナーレポート
今回は、昨年末に開催した九鬼靖太先生による無料ウェビナー「Contextual Strength Training の基礎と応用 -ヒップロックの徹底解説-」の内容の一部をご紹介します。 ベーシックな筋力トレーニングと競技動作の間を埋める“中間領域”として注目を集めるCST(Contextual Strength Training)。 本講義ではその理論的背景と実践的アプローチをもとに、CSTの中核をなす「ヒップロック」について詳しく解説いただきました。 ■テーマ:Contextual Strength Training の基礎と応用 -ヒップロックの徹底解説- ■開催日:2025年12月28日 ■講師:九鬼 靖太 (大阪経済大学 人間科学部 准教授、CST講師) CST(Contextual Strength Training)とは? CSTとは、競技パフォーマンス向上を目的とした文脈的ストレングストレーニングであり、以下の3つの要素を統合したアプローチを指します。 1.特異的な負荷の提供 - 筋力トレーニングや競技動作の反復だけでは得られない負荷を与える。 2.運動学習の理論活用 - 競技動作のコアとなるアトラクターを学習し深化するための学習機会を提供する。 3.競技動作への転移 - 実際の競技場面で発揮される動作を意識したトレーニングを構築する。 以上の内容を網羅的に学習するために、DMC(動的運動制御)、MLT(運動学習理論)、SSM(競技特異的動作)の3コースを認定しています。...
ヒップロックを徹底解説!(九鬼 靖太先生)|ウェビナーレポート

メディシンボールの活用法|Michael Boyle氏寄稿
日々新たなトレーニングツールが増えていく中で、ツールごとの重量や数量をどの導入すればよいのか?または器具ごとの特性や違いに悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は Mike Boyle Strength & Conditioning(MBSC)の創設Michael BoyleがPERFORM BETTER本社のブランドサイトに寄稿した「The Benefits of Soft Toss Medicine Balls(ソフトトスメディシンボールの利点)」をご紹介します。既に多くの施設やチーム、個人に導入いただいているソフトトスメディシンボールの活用法や従来のメディシンボールとの使い分けも紹介しておりますのでぜひ最後までご一読ください。 ソフトトスメディシンボールの利点 メディシンボール、特に「ソフトトス(柔らかい素材)」のメディシンボールは、私のお気に入りのトレーニングツールです。 しかし、実は最初からそうだったわけではありません。 約10年前、私は上半身のプライオメトリックトレーニングを目的に、重いメディシンボールを導入しました。主に行っていたのは、1人がボールを落とし、もう1人がそれを受け止めて投げ返す「メディシンボール・ベンチプレス」です。 この種目は、プライオメトリクス腕立て伏せのように肩へ過度なストレスをかけることなく、上半身のパワーを高められる点が気に入っていました。 そこで使用していたのが、落としても扱いやすく、衝撃が手に伝わりにくい柔らかい球質のメディシンボールでした。 数年前、スタッフの1人が若いアスリート向けに軽量のソフトトスメディシンボールをいくつか発注してくれました。しかし、それらはしばらく倉庫の奥に置かれたままになっていました。 「いつ使うことになるのだろう?」と思いながらも、せっかく購入したのだからと、活用方法を模索していました。 ある日、思い立ってそれらの軽いボールを取り出し、壁に向かって横回転のスローを行ってみたのです。 通常、このような回旋(ローテーション)系のスローは、体幹の爆発的パワーを高める目的で行われ、弾むラバーボールを使うのが一般的です。 正直なところ、最初の印象はこうでした。 「これは最悪だ。まったく跳ね返ってこない。」 実際、わずかに跳ね返ってきたとしても、その反応は非常に弱いものでした。 しかし、その瞬間にひらめいたのです。...

サミットレポート(3/3)|PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2025
日頃よりパフォームベタージャパンをご愛顧いただきましてありがとうございます。 10月17日(金)〜19日(日)に開催した「PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2025」の内容の一部を全3回に分けて配信させていただきます。 今回は2日目の講義の模様を一部ご紹介します。 初日に続き運動指導をはじめ多様な分野の専門家に講師としてご登壇いただきました。 理論から実践、現場への応用まで多角的に掘り下げた講義が行われました。 テーマ:モーターコントロールマトリクス:姿勢・動作の再構築を目指した5階層モデル2025年版 近藤 拓人(AZCARE 代表/NEXPORT 代表) 近藤さんは、日米のスポーツチーム、クリニック、フィットネス施設での豊富な経験を基に、現在はAZCARE ACADEMY代表およびパーソナルトレーニング施設NEXPORT代表として、現場指導と教育活動に従事されています。 本講義では感覚運動科学を基盤とし、姿勢・動作を再構築するための概念「モーターコントロールマトリクス」を解説いただきました。 各階層(屈曲・伸展・回旋・側屈・並進)における評価・トレーニング法を整理することで、安全かつ効率的なアプローチを可能にします。 各階層で求められる評価視点やトレーニング手法を動画を交えご紹介いたしました。 パフォーマンス向上、姿勢改善、傷害予防など、目的に応じた戦略的な介入の全体像が理解できる内容でした。 テーマ:Postural Restorationの視点で捉える回旋運動と実践的アプローチ 石井 健太郎(PRI Japan合同会社代表 / クリニカルラボ・スリーアール代表) 石井さんは、男子サッカーアメリカ代表のアスレティックトレーナーとして活動する一方で、日本ではクリニカルラボ・スリーアールで臨床活動を行っています。 「人を人として見る」ことを信条とし、Postural Restorationのコンセプトを基に障害予防を探究し、治療とパフォーマンストレーニングのギャップを埋める取り組みに注力されています。 本講義では、PRIの臨床概念をもとに、人体の左右非対称性と回旋運動の関係性を解説いただきました。...

vol.16 動画|スーパーバンドを使用したエクササイズバリエーションのご紹介
今回はオンラインショップで公開中の「MINI BAND & SUPER BAND Lab.」より、スーパーバンドを使用したエクササイズバリエーションをご紹介いたします。 エクササイズの目的や重要なポイントなども詳しく記載しておりますので、ぜひ最後までチェックいただけますと幸いです。 Single Leg Jammer 目的・エクササイズ特性 ・下肢の強化(レジスタンス)+体幹部の安定・加速時の爆発的動作 ターゲット 臀筋群・大腿四頭筋・ハムストリングス・コア 使用アイテム ・スーパーバンド 1.9cm幅 イエロー ・フォームプライオボックス H61cm 動作手順 1.スーパーバンド2本を、両肩にそれぞれ掛けて立つ。2.スーパーバンドの片側をパワーラックにかけもう片方を肩にかけます。3.スクワットのようにしゃがみ、斜め前方へジャンプするように爆発的に膝・股関節を伸展する(片足だけ)。4.伸展後は、前方に置いたボックスに手をつき、元に戻る。 重要なポイント ・ニーインを起こさないようにする。・膝関節+股関節伸展を同時に行いコーディネートされた(協調性のある)求心性収縮を爆発的に行う。 コーチングキー 片足で地面を爆発的に蹴り、対側の脚を前方へ膝蹴りするイメージを持つ。 よくあるエラー 腰部伸展 Resisted Lever...
vol.16 動画|スーパーバンドを使用したエクササイズバリエーションのご紹介

ウェビナー質疑応答を公開!|感覚運動科学の基礎(近藤 拓人先生)
今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。 感覚運動科学の基礎から実践的な応用までを丁寧に解説し、現場で役立つ知識やスキルについて具体的にお話しいただきました。 今回のレポートではウェビナー終盤に受講者から寄せられた質問とそれに対する近藤先生の回答をまとめています。 本テーマは2024年12月、今年4月、8月にも実施されており、基本構造や理論の整理については、以下のコラム記事にてご紹介しています。 ウェビナーレポート|近藤 拓人さん「感覚運動科学の基礎」 ご参加いただけなかった方や、復習したい方は是非あわせてご覧ください。 ■テーマ:感覚運動科学の基礎 ■開催日:2025年11月15日 ■講師:近藤 拓人 (AZCARE ACADEMY 代表 / NEXPORT 代表) Q&A 感覚運動科学の理解をベースにウェビナー後半では医療・トレーニング・フィットネスといった多様な現場から寄せられた質問に対し、近藤さんが理論と実践をつなぐかたちで丁寧にご回答をいただきました。 以下、一部抜粋してご紹介します。 Q1:眼球運動に関してもPLAZ+で学ぶことができますか? A: はい、学べます。 視覚の講座は後藤先生が担当してくれていますが、まずは僕の講座を受けたあとに、後藤先生の12回コースを受けてもらうのが一番いいです。 ただ眼球運動だけを学んで現場で使うのはおすすめしません。 リスクもありますし、結局使わなくなるからです。 視覚そのものを理解した上で眼球運動を使うと、すごく効果的なのでその意味でも PLAZ+ではしっかり学べる内容になっています。 Q2:背面(広背筋、ハムストリングスなど)の感覚を感じづらい方が多いと感じます。日常の体感覚視覚からの情報が少ないからでしょうか? A: イメージもあると思いますが、実は広背筋より腹筋群のほうが感覚が薄いです。 特に腹筋下部が全然わからないという方がめちゃくちゃ多いです。 ほかにも前鋸筋、僧帽筋下部、内側広筋、上腕三頭筋など、感覚の入力が入りづらい筋肉っていくつかあります。 なので、背面だから弱いというよりは、そもそも体勢感覚として情報が入りにくい部位が人によって決まっているというイメージのほうが近いですね。...
ウェビナー質疑応答を公開!|感覚運動科学の基礎(近藤 拓人先生)

サミットレポート(2/3)|PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2025
10月17日(金)〜19日(日)に開催した「PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2025」の内容の一部を全3回に分けて配信させていただきます。 今回は初日の講義の模様を一部ご紹介します。 栄養、コミュニケーション、感覚運動、多方向ムーブメントなど多角的なテーマを通じ、現場で活用できる知見を解説いただきました。 テーマ:ダイエットのための栄養学(前半)/EAMC(運動関連筋痙攣)に対する統合療法(後半) 川合 智(日本統合療法株式会社 代表) 川合さんは運動療法と栄養療法を土台とした「統合療法」を指導し、様々な慢性不調を抱える方を寛解へ導き、アスリートに対する栄養アドバイスも行っています。 前半の講義では、ダイエットを「体重減少」ではなく「代謝の調整」として捉える考え方を紹介しました。 ダイエット成功のために押さえておきたい栄養学的アプローチを、マクロ(エネルギーフラックス、セットポイント理論など)とミクロ(慢性炎症、血糖コントロール、微量栄養素欠乏など)の二つの視点から解説しました。 後半の講義では、運動関連筋痙攣(EAMC)と熱痙攣との違いを整理した上で、EAMCに関連する栄養素について解説しました。 栄養アプローチを“現場で扱える言語”に落とし込む重要性を伝え、実践につながる学びとなりました。 テーマ:Reach Program −知識・技術だけでは足りない、現場で求められる成果を引き出すコミュニケーションの力− 荒井 秀幸(株式会社R-body Chief Technical Officer) 荒井さんは、コンディショニングを提供するスポーツ運動療法施設「株式会社R-body」のChief Technical Officerとして、トップアスリートや一般の方に向けたコンディショニングトレーニング指導を行っています。 本講義では「知識や技術だけで成果は出ない。必要なのは“伝え方の力”」と語りR-bodyが開発したReach Programをもとに、コーチングとティーチングの違いを明確に整理し、クライアントの行動変容を引き出すための“再現性あるコミュニケーション”の仕組みを紹介しました。 会場では多くの受講者が実際のケーススタディを通して、言葉の使い方が結果を左右することを体感していました。 テーマ:関節アライメントを考慮した連動性とパフォーマンスの向上 −運動感覚を培うために−...

ケトルベルを活用したパワーエンデュランストレーニング|Jason C. Brown氏寄稿
日々新たなトレーニング理論が増えていく中で、インプットした内容を日常のクライアント指導にどう活かせばよいのか悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本コラムでは、最新のトレーニング理論やそれを現場に活用するために必要な器具をご紹介します。ぜひ、日常の指導にお役立ていただけますと幸いです。 今回はフィットネス、スポーツ分野におけるケトルベルトレーニングの国際的な第一人者であり、フィットネス専門家向けプログラム「Kettlebell Athletics Certification」創設者のJason C. Brownが、PERFORM BETTER本社のブランドサイトに寄稿した『ケトルベルを使ったパワーエンデュランストレーニング』をご紹介します。既に多くの施設やチーム、個人に導入いただいているケトルベルのトレーニングプログラムの考え方を紹介しておりますのでぜひ最後までご一読ください。 ケトルベルを使ったパワーエンデュランストレーニング (著:ジェイソン・C・ブラウン) ほとんどのスポーツ競技は、長い時間にわたって爆発的な動きを生み出す能力を中心に展開されます。この運動能力は「パワーエンデュランス(Power Endurance)」として知られています。パワーエンデュランスのトレーニングは非常に過酷ですが、最も高いパワーエンデュランスを持つアスリートが、最終的に勝利を収めることが多いのです。 ケトルベルトレーニングは、スポーツパフォーマンス向上の分野では比較的新しいトレーニング方法です。しかし、パワーエンデュランスを向上させるためのトレーニングツールを1つ選ぶとすれば、それはケトルベルでしょう。 ケトルベルトレーニングは、伝統的に修正されたオリンピックリフトのバリエーションを高回数で行うことを中心に構成されています。この高回数と修正版オリンピックリフトの組み合わせこそが、ケトルベルトレーニングをパワーエンデュランス向上に理想的な方法にしているのです。 では、この組み合わせがなぜ効果的なのでしょうか? オリンピックリフトおよびそのバリエーションは、その設計上、ゆっくりと行うことはできません。スナッチ、クリーン、ジャークといった動作は、素早く実行しなければなりません。この高速リフティングのプロトコルを組み合わせることで、長時間にわたって高い出力を生み出すよう身体を訓練することができます。 ケトルベル・クラスター(Kettlebell Clusters) ケトルベル・クラスターでは、一定の時間内に20秒ごとに1回の反復を行います。さらに刺激を加えるために、私はよく1回ごとに異なるドリルをローテーションさせます。 たとえば、最初の反復ではスナッチを行い、20秒休み、次にクリーンを行い、さらに20秒休んでハイプルを行う、といった具合です。 パートナーと一緒にケトルベル・クラスターを行うのも非常に良い方法です。互いに次の反復で行うドリルをコールし合うことで、ワークアウトに少しの混乱と多くの楽しさを加えられます。また、お互いが競い合うことでより熱のこもったトレーニングになります。 ただし、選ぶドリルは爆発的で素早く実行でき、パートナーのスキルに適したものであることが重要です。 1分間のケトルベル・クラスターの一例をご紹介します。 ケトルベル・スナッチ ×1回 → 20秒休憩ケトルベル・クリーン&ジャーク ×1回 → 20秒休憩ケトルベル・プッシュプレス...
ケトルベルを活用したパワーエンデュランストレーニング|Jason C. Brown氏寄稿

vol.15 動画|スーパーバンドを使用したエクササイズバリエーションのご紹介
今回はオンラインショップで公開中の「MINI BAND & SUPER BAND Lab.」より、スーパーバンドを使用したエクササイズバリエーションをご紹介いたします。 エクササイズの目的や重要なポイントなども詳しく記載しておりますので、ぜひ最後までチェックいただけますと幸いです。 Scapular Adductor Stretch 目的・エクササイズ特性 ・肩甲骨周囲のストレッチ・胸郭モビリティーの向上 ターゲット 菱形筋・僧帽筋中部 使用アイテム スーパーバンド 0.7cm幅 オレンジ 動作手順 1.スーパーバンドを背中を通して右肩につける。2.右膝をついて、左足を外転して地面につき、体を支える。3.左手を地面につき、右手を頭の後ろにおく。4.胸郭を右回旋・左回旋し、肩甲骨周囲のストレッチと胸郭の回旋を行う。 重要なポイント ・脊柱のニュートラルポジションを維持する。・胸椎回旋を意識する。 コーチングキー 脊柱の長軸を意識し軸上でコマのように回旋する。 よくあるエラー 体幹部側屈が入る セッティング手順 ・スーパーバンド2本を結ぶ。・スーパーバンドをラックにつける。 Jammer 目的・エクササイズ特性...
vol.15 動画|スーパーバンドを使用したエクササイズバリエーションのご紹介

サミットレポート(1/3)|前日カンファレンス
10月17日(金)〜19日(日)に開催した「PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2025」の内容の一部を全3回に分けてご紹介させていただきます。今回は前日カンファレンスついてご紹介します。 北島康介をモデルケースに「アスリートの身体評価をアップデート」のテーマでディスカッションを実施しました。 まずは現役時代に競泳日本代表のトレーナーとしてコンディショニングを担当してた小泉圭介さん、現在、実際にトレーニングに通うBest Performance Laboratoryの桂良太郎さんにスライドを使いながら講義いただき、近藤拓人さんにはその場で初めて北島康介の身体を評価いただきました。 アスリートの身体評価をアップデート -現役期・引退後の目的の目的の変化に応じたトレーニング戦略 1.小泉圭介 現役時代の課題と取り組み 小泉さんからは当時の北島康介の身体評価から実際に取り組んだエクササイズをご紹介いただきました。当時の身体評価の画像やレース中の映像も交え、非公開情報も含めた内容で現役時代の北島康介の特徴や課題を振り返しました。 2.桂良太郎 現在のトレーニングプログラム 桂さんからはBest Performance Laboratoryの身体評価システムやトレーニングプログラムから、現在の身体の課題解決や、仕事とプライベートを充実させるために取り組んでいるトレーニングをご紹介いただきました。 3.近藤拓人 初めて対応するアスリートの身体評価 近藤さんには小泉さん、桂さんのお話を受けたうえで北島の身体を評価しながら、初めてクライアントを身体評価をするうえでのポイントや順序などを自身の施設「NEXPORT」でも取り組んでいる内容も踏まえてご紹介いただきました。 現役期と現在で共通する胸椎、脊柱のモビリティの課題 現役期から今に至るまで身体の特徴である胸椎や脊柱の可動性についてそれぞれの見立てや、エクササイズ戦略をディスカッションしました。 北島本人が現在感じている「背中の違和感」との関連性などそれぞれの見立て、戦略と実際のエクササイズもご紹介いただきました。 アスリートとの関わり方「競技特異性」について アスリートと関わるうえでは必ず話題に出る「競技特異性」についてもディスカッションが行われました。特定の部位を鍛えたり、エクササイズなどの目先のテクニックに頼るのではなく、まずトレーナーの立場としては競技そのものの理解度よりも、「競技動作のバイオメカニクスを理解する力」の重要性が述べられました。 アスリートに求められるリテラシーとセルフマネジメント力 北島からは、「アスリートが判断すべき部分と、身体に関してはトレーナーに委ねる部分を自分自身で整理することが大切で、トレーナーの知識、技術を活かすにはアスリートのリテラシー次第で大きく変わる」と意見がありました。 現役時代を振り返り、セルフマネジメント力とリテラシー、またトレーナーを含めた周りのスタッフとの信頼関係が相互に支え合うことで、コンディションやパフォーマンスを長期的に維持するには重要であることが再認識されました。...
サミットレポート(1/3)|前日カンファレンス

Webinar Report|AIを用いたスポーツ動作解析(内田 智也先生)|サミットプレウェ...
今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。 トヨタアスリートスポーツセンターの内田智也先生に「AIを用いたスポーツ動作解析」をテーマに講義いただきました。 本ウェビナーは10/18~19に開催するパフォームベタージャパンサミット2025のプレウェビナーになりますので、ご検討中の方は参考になれば幸いです。 ■テーマ:AIを用いたスポーツ動作解析 プレウェビナー編 ■開催日:2025年8月28日 ■講師:内田 智也 (トヨタアスリートスポーツセンター) AIを用いた動作解析とは? 近年、AI技術の進歩により、スポーツ動作解析の方法は大きく変化しています。 従来のマーカーを体に貼り付けるモーションキャプチャーは準備や後処理に時間がかかり、研究用途が中心でした。 しかし、AIによる「マーカーレス解析」が登場したことで、カメラ撮影だけで短時間に解析が可能になり、現場での実用性が一気に高まりました。 特に投球動作のような複雑な動きでも、5分程度で解析とフィードバックが行えるようになり、病院やチームの現場でも導入が進んでいます。 動作解析は評価の一部 筋力測定や関節可動域の評価、画像診断などと同様に、動作解析も統合的な評価の一つであり、それ単体で完結するものではありません。 特に重要なのは、数値そのものよりも「どの変数を選び、どのように解釈して伝えるか」。 対象者に合わせたフィードバックが必要であり、プロ選手から学生、一般の方まで、理解度に応じて伝え方を変える工夫が求められます。 リアルタイムフィードバックシステム トヨタアスリートサポートセンターでは、フォースプレートやジャンプ計測、アイソメトリックスクワットなどを組み合わせ、AI解析と統合した「リアルタイムフィードバックシステム」を構築しています。 たとえば片脚ジャンプや減速動作を評価し、着地時の膝や股関節の使い方を数値化。 さらに直感的に理解できるよう姿勢や体幹の傾きをビジュアルで提示することで、選手自身が動きを修正しやすくなる仕組みを導入しています。 このように「わかりやすいアウトプット」を設計することが、選手の納得感と現場での活用につながっています。 Bridge the gap AIを用いた動作解析は高精度かつ短時間で可能になりましたが、それを「どう現場に落とし込むか」が大きな課題です。 解析者が提示する変数やフィードバック方法に専門性の偏りが出ると、現場とのギャップが生まれる可能性があります。 その橋渡し役となるのが、指導者やトレーナーです。 選手やコーチの言語と、解析から得られる数値をつなげることが、AI時代の動作解析において欠かせない要素といえます。...
ジム開業・改装などを
検討中の方へ

施設見学・一括お見積もりを承っております
導入器具に関するご相談はもちろん、物件選びや施設レイアウト、床材の選び方などの初期段階からご相談いただけます。時期未定、構想段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
詳しく見る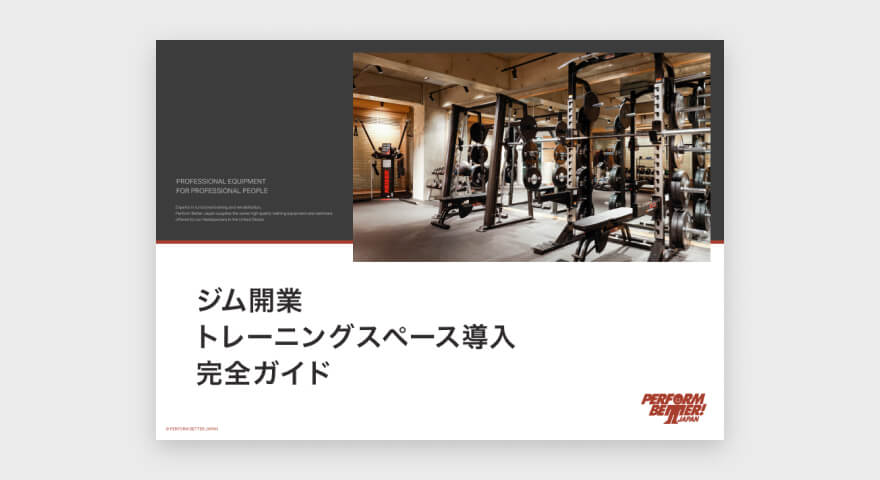
無料のお役立ち資料を配布しております
物件選びや床材の選び方、施設レイアウト、器具の選定などで押さえておきたいポイントをまとめた全30ページの資料です。ジムの開業や、トレーニングルームのリニューアルを検討している方にもお役立ていただけます。
PDFをダウンロードする