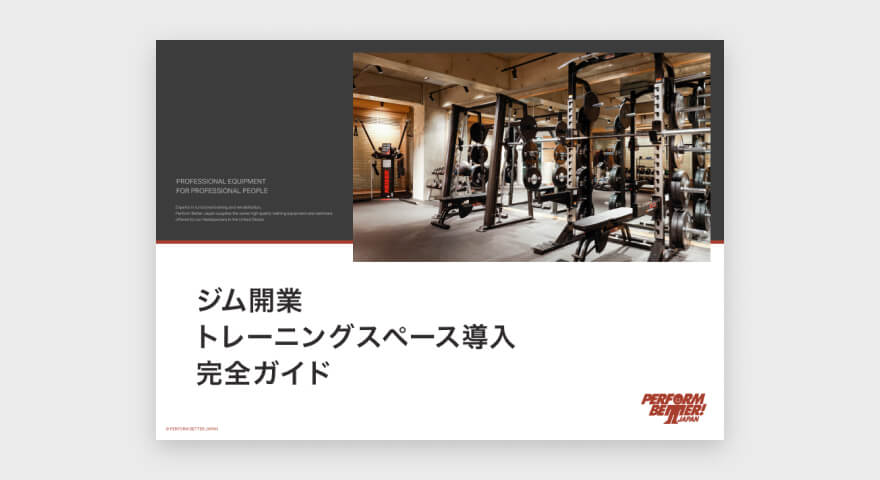今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。
感覚運動科学の基礎から実践的な応用までを丁寧に解説し、現場で役立つ知識やスキルについて具体的にお話しいただきました。
今回のレポートではウェビナー終盤に受講者から寄せられた質問とそれに対する近藤先生の回答をまとめています。
本テーマは2024年12月にも実施されており、基本構造や理論の整理については、以下のコラム記事にてご紹介しています。
ウェビナーレポート|近藤 拓人さん「感覚運動科学の基礎」
ご参加いただけなかった方や、復習したい方は是非あわせてご覧ください。
■テーマ:感覚運動科学の基礎
■開催日:2025年4月13日
■講師:近藤 拓人 (AZCARE ACADEMY 代表 / NEXPORT 代表)
感覚・神経・運動を“情報の流れ”としてとらえる視点
運動を「筋肉を動かすこと」ではなく、感覚(入力)→ 神経系の判断 → 運動(出力)という一連の情報処理の流れとして捉える視点をもたなくてはなりません。
動きの質や学習を高めていくためには、目に見える出力だけではなく、「何を感じ取って、どんな判断を経て、その動きが生じているのか」までを含めて理解することが重要です。 このような視点が、医療・トレーニング・フィットネスなどあらゆる現場でのより本質的な評価と指導につながるとされています。
Q&Aセッション
感覚運動科学の理解をベースにウェビナー後半では医療・トレーニング・フィットネスといった多様な現場から寄せられた質問に対し、近藤さんが理論と実践をつなぐかたちで丁寧にご回答をいただきました。
以下、一部抜粋してご紹介します。
Q1:感覚運動科学は初めて聞いたお話しでしたが、今回の講義のようなアプローチをパーソナルトレーニングで提供する場合は、医療機関と提携すべきでしょうか?近藤さんが医療機関と提携されている内容や注意事項があれば教えてください。
A:
提携は手段であって目的ではありません。
目的は「クライアントに安全で適切な運動を提供すること」です。
疼痛や内科的リスクの管理が必要な場合は、相談できる医療機関があると安心ですが、 基本的には必要なタイミングで連携できる関係性があれば十分です。
私たちの施設でも、必要なケースのみ医師やセラピストと情報を共有する体制をとっています。
Q2:オンラインサロン(PLAZ+)と合わせてピラティスの講座を受講するか検討しています。未経験者でも大丈夫でしょうか?
A:
はい、大丈夫です。
ピラティス講座は未経験者でも段階的に学べる設計になっていますし、感覚運動科学との親和性も高く、身体感覚や動作コントロールを深める入り口としてもおすすめです。
「どう動かすか」ではなく「どう感じるか」にフォーカスできる点が、他の手法と異なる魅力だと思います。
Q3:LSD(Long Slow Distance)はどの有酸素種目がおすすめですか?
A:
クライアントの目的や身体の状態によって使い分けます。
関節への負担を減らしたいならバイク、感覚入力を高めたいならウォーキングなど、何を得たいかによって有酸素の選択は変えるのが基本です。
種目よりも「目的に対してどう位置づけるか」がポイントです。
Q4:感覚器の問題であることをトレーナーが認識し、パーソナルトレーニング中にそれを改善しようとすると一般の方の場合はエクササイズやセッションが退屈になるのではと懸念があります。セッション中の時間の使い方の問題もあると思いますが近藤さんが工夫していることはありますか?
A:
クライアントが何を目的に来ているかを見極める必要があります。
トレーニングをすること自体が目的ではなく、自身の課題を解決することが目的である場合が多いです。
だからこそ、なぜこのエクササイズを行うのかを理解してもらうことが重要です。
もし退屈に感じさせてしまうとすれば、選んでいるエクササイズやその伝え方が療法としてズレている可能性があります。
クライアントにメリットを感じてもらうには、エクササイズの用途と役割を正しく理解し、わかりやすく伝えることが前提です。
Q5:有酸素運動以外で低酸素室を活用されていますでしょうか?
A:
本来は低閾値の運動を低酸素環境下で行いたいと考えていますが、NEXPORTの低酸素室には複数の有酸素マシンが設置されているため、スペース的に現状は難しい状況です。
そのため、低閾値の運動は主にピラティスエリアで提供しています。
なお、低酸素室に十分なスペースがある場合は、低閾値の運動は非常に有効です。
酸素濃度の調整で中枢系への負荷を微細にコントロールできるのも利点です。
Q6:可動域はあるけど痛みがあって動かせない場合、痛みがない範囲でトレーニングをするのが良いですか?
A:
原則として痛みのない範囲で成功体験を積み重ねることが大切です。
それによって「動かしても大丈夫」という感覚が育ち、結果的に可動域も自然と広がっていくことが多いです。
むしろ、「痛みがない中で動けた」という認識を強化すること自体が介入になります。
前回(2024年12月開催)の講義内容はこちら
本テーマは2024年12月にも開催されており、講義内容や基本概念については以下のコラムでご覧いただけます。
今回の内容とあわせて、復習や理解の整理にぜひご活用ください。
株式会社パフォームベタージャパン