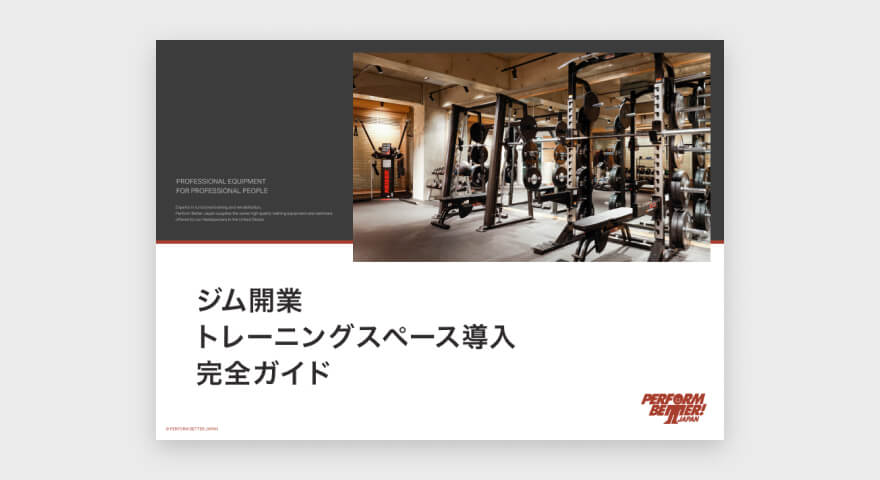PERFORM BETTER JAPANの石田です。
今回はPERFORM BETTER JAPAN SUMMITを受講するうえでのポイントをアメリカ本社が主催する「PERFORM BETTER SUMMIT」の事例も交えてご紹介いたします。
今年も8月14日(水)〜16日(金)の3日間、本社が所在するロードアイランド州で開催されるSUMMITに私も参加予定です。
ロードアイランドでの開催は、これまでのシカゴ、ロングビーチに続き、3都市目となります。
PERFORM BETTER SUMMITとは
PERFORM BETTER SUMMITは20年以上前から毎年アメリカ各地で開催している3日間のセミナーで、各会場で30名近い講師が登壇し約1,000人の受講者が参加します。
登壇する講師はアスレティックトレーナー、S&Cコーチ、理学療法士、フィットネスインストラクター、栄養士、元アスリートなど資格、職種ともに多岐に渡ります。
受講者は講師同様の資格、職種に加えて、中学、高校の先生やフィットネス愛好家など日本のセミナーではあまり見かけない業種の人たちも多く参加しています。
会場ではLecture roomとHands-onのそれぞれ2部屋が用意されており、合計で4つのセミナーが1コマあたり75分で同時に進行していきます。
受講者は自分の好みのセミナーを毎時間ごとに選択しますが、セミナールームの出入りは自由なため、お目当ての講師、初めて受講するテーマ、または自分の専門外のテーマのセミナールームに入ったりと多種多様な受講方法でサミットを楽しんでいます。
日本でも2018年からPERFORM BETTER JAPAN SUMMITを開催しており、毎年 150 名以上の受講者が新たな学びや、受講者同士の交流を求めてサミットへ参加していただいています。
講師、受講者の輪を拡げ、日本では「トレーナー」と呼ばれる職業の中に多くある資格の垣根を越えた情報交換、交流、学びの場とすること を開催の目的としています。

PERFORM BETTER SUMMITの受講者
私が初めて本社のSUMMITに参加したのは2016年のロードアイランドでした。
その時は日本からツアーを組み、総勢20名でツアー参加者と講師兼通訳のみなさんと一緒にSUMMITを受講しました。
アメリカ本社の受講者の特徴としては前述の通り職種が多種多様な点です。
日本の受講者でも多いアスレティックトレーナー、S&Cコーチ、理学療法士はもちろんですが、中学、高校の先生やフィットネス愛好家、フィットネスインストラクターなど日本ではあまり見かけない業種や資格の人たちが自身の学びと受講者同士のつながりを求めて参加しています。
SUMMITの特徴
1.Hands-on(実技)
SUMMITの1番の特徴はPERFORM BETTER製品を活用した実技セミナーです。
会場内にはミニバンド、スーパーバンド、ケトルベル、メディシンボールなどの定番商品はもちろん、SUMMITが開催される時期の新商品も準備されていて、講師が運動指導で実践している活用法も紹介されます。
受講者が複数のグループになり、トレーニングしながらお互いの身体の動きをチェックしながら講師の説明をお互いに確認し合います。

2.Lecture(講義)
先に述べた通り1番の特徴は実技ですが、ただ器具の使い方を紹介するわけではありません。
前後で行われる講義では「なぜそのエクササイズが必要なのか?」「どのケースでこの器具を使うべきなのか?」など根拠となる背景が講義で紹介されます。
PERFORM BETTERの器具は使い方が無限にあるものや、一見すると使い方が分からないものもあります。
それゆえにただ使い方だけを紹介すると正しい知識や技術が拡がらないため、実技の根拠を説明する講義が必要となります。
受講者からも「このケースではどうするのか?」「このケースだと〇〇がいいと思うが、見解を教えてほしい」など質問が頻繁にでます。
そして、多くの受講者が「先ほどの講義ではAと紹介していたが、私はBだと思う。Aだと思う根拠をもう一度詳しく聞かせてほしい」など、自身の見解を述べながら質問するのがアメリカのSUMMITではとても特徴的です。
質疑応答中はもちろんですが、講義の合間にも講師と受講者、または受講者同士でも活発な議論が行われています。
日本ではアメリカほど質問が止まらないような状況は少ないですが、それでも講義の合間などに講師、受講者と議論をしているケースを目にします。

3.学びたい理論や講師を決める
ここまでご紹介してきた通り、各講師が自分の理論や技術を講義と実技を交えてそれぞれセミナーを実施しますが、限られた時間なので講師の伝えたいこと、受講者の学びたいことのすべてが伝わるわけではありません。
SUMMITの受講者は3日間で細かくすべての情報を収集するわけではなく、最先端の理論、技術、知識のイントロダクションをインプットしてその後に誰から何を学ぶかを検討するための情報を収集しています。
SUMMITに登壇する講師のほとんどが自身のセミナーやアカデミー、資格発行をおこなっているため、受講者は自分が次に必要な理論、技術、知識をみつけて後日それぞれ講師が開催するセミナーに参加し自己の研鑽に活かしています。
特に20代の受講者は自分自身がこれからどの分野を追求していきたいか、専門家としてどのポジションでクライアントや社会に貢献していきたいかの方向性を決めるうえでの参考になるとても良い機会になっています。
日本でのサミットも同様にそれぞれの講師からのイントロダクションセミナーとなりますので、詳しく学習したい方は講師が主宰するアカデミーやセミナーへの受講をお勧めいたします。
複数の講師からの情報を理解するヒント
最後に複数の講師から情報を得る際に気を付けるヒントを2点ご紹介いたします。
いずれも私の意見ではなく、これまでセミナー活動に携わってきた中で、講師から受講者へのアドバイスとしてよく語られているものです。
「違い」よりも「共通点」に着目する
Q1.複数の講師の話を聞くと違うことを言っている気がして混乱します。解決策があれば教えて欲しいです。
A1.それぞれの背景や職業、資格によって一見すると異なることを話しているように感じることもあると思います。
また、講師が話す内容の前提が違うことも十分考えられるためにそれも考慮する必要があります。
そのうえで、複数の講師からの情報を学ぶにあたり「異なる点」に先に目を向けるのではなく「共通点」に先に注目してみてください。
登壇する講師の背景や職業、資格が違っても必ず何か共有点があるはずです。
必要に応じて質問をしたりして、それらを把握したうえで「異なる点」に目を向けるとご自身の解釈がまた変わると思います。
自分の知識・経験はいったん傍に置いて講師の話を聞く
Q2.自分の資格と異なる講師の場合、講義内容が自分のクライアントに当てはまらないケースが多くあります。サミットで講義を選択するポイントを教えて欲しいです。
A2.自分が学びたい内容の講義を受けるのが1番ですが、迷う場合や自分と異なる分野の専門家の話を聞く場合のポイントを回答いたします。
受講するうえでは自分のクライアントに当てはめたり、自分の専門知識で解釈するのも大事ですが、まずはその講師が何を紹介しているのかを理解することを優先してください。
「自分のクライアントには当てはまらない」「自分の学んできたことと違う」やその講師が話している例外から考えるのではなく、講義の主たる学習内容をしっかりと把握したうえで、取捨選択するようにしないと、学習の幅を狭めて結果的に学びも浅くなってしまいます。
2016年には日本からロードアイランドのSUMMITへ参加するツアーを企画しましたが、また機会があれば渡航者を募って本社のSUMMITに皆さんとご一緒できればと思います。
そして、日本で開催する今年のPERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2025は10/17~19の三日間です。
PERFOR MBETTER JAPANサミット 2025はこちらからお申し込みください。
https://www.performbetter.jp/products/s0098
初めての方でもお気軽にご参加いただけるよう、サミットの楽しみ方もコラムでご紹介していますのでぜひチェックしてみてください。
サミットの楽しみ方はこちら
株式会社パフォベタージャパン