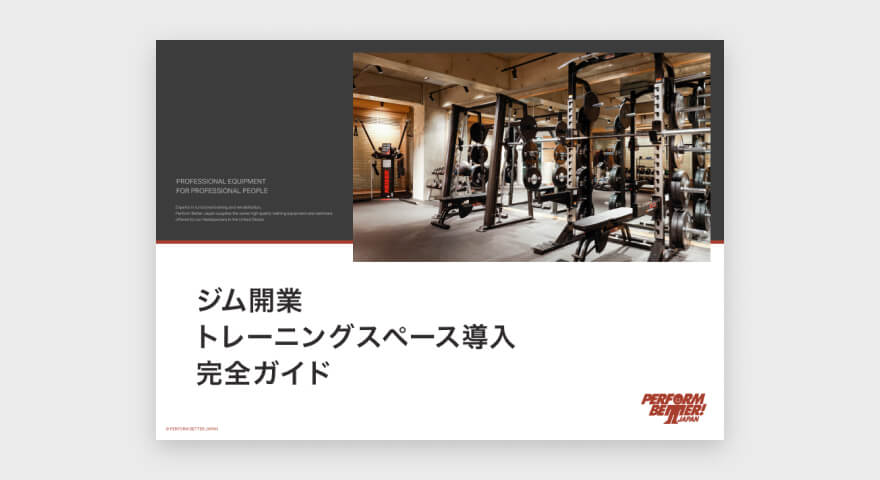日々新たなトレーニング理論が増えていく中で、インプットした内容を日常のクライアント指導にどう活かせばよいのか悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、最新のトレーニング理論やそれを現場に活用するために必要な器具をご紹介します。ぜひ、日常の指導にお役立ていただけますと幸いです。
今回は Mike Boyle Strength & Conditioning(MBSC)の創設Michael BoyleがPERFORM BETTER本社のブランドサイトに寄稿した「Using Foam Rollers(フォームローラーの活用)」をご紹介します。
既に多くの施設やチーム、個人に導入いただいているフォームローラーの活用法や効果を紹介しておりますのでぜひ最後までご一読ください。
はじめに
20年前、ほとんどのストレングスコーチやアスレティックトレーナーは、長さ90cmほどの円柱状のフォームローラーを見て、「これは何のためのものか?」と首をかしげていたことでしょう。
それが現在では、ほぼすべてのアスレティックトレーニングルームや多くのストレングス&コンディショニング施設に、長さや硬さの異なる複数のフォームローラーが備えられています。
フォームローラーの普及の背景
フォームローラーが広く使われるようになったのは、マッサージに対する意識の変化によるものです。
これまで私たちは、アイソキネティクスや電子機器を用いた怪我へのケアを中心にアプローチを行ってきましたが、より欧州的な手技による軟部組織のケアへと徐々にシフトしてきました。
現在では、マッサージ、 Muscle Activation(MAT)、アクティブリリース(ART)などが、痛みや怪我を抱えたアスリートに非常に有効であることがわかっています。
エリートアスリートの間では、「健康を維持したければ、信頼できるマニュアルセラピストを味方につけるべき」という認識が一般的です。
そのため、あらゆるレベルのアスリートが何らかの形で軟部組織のケアを求めるようになっています。
フォームローラーの意義
フォームローラーは、軟部組織へのケアの恩恵を大人数のアスリートに効率的に提供する手段として注目されました。
エリートアスリートがさまざまな好影響を受けるのを見たコーチたちが、「大人数のアスリートに手頃なコストでマッサージを提供する方法は?」というを悩みから、フォームローラーの導入に至りました。
National Academy of Sports Medicine の会長、Michael Clark 博士(DPT, MS, PT, NASM-PES)は、スポーツ医療のコミュニティにフォームローラーを広めた人物の一人として知られています。
Clark博士の初期のマニュアルには、フォームローラーを使ったセルフ筋膜リリースの写真が掲載されてしましたが、フォームローラーを使い、体重を利用して筋肉の痛みのある部位に圧をかけるシンプルで明白な手法でした。
現在の活用と進化
その後、多くのコーチやトレーナーがフォームローラーのさらなる活用法を見出し、怪我予防やパフォーマンス向上にも効果的に使われています。
また、当初の指圧的な使い方から、よりセルフマッサージ的な使い方へと移行し、状況に応じた具体的な活用法も考案されています。
基本的に、フォームローラーは「低コストのマッサージセラピスト」と言えます。
あらゆる環境で軟部組織のケアを提供できますが、最大限の効果を得るためには特性や使い方を理解する必要があります。
フォームローラーとは
フォームローラーは、硬質発泡フォームを円柱状に成形したものです。
プール用のヌードルのような形状ですが、密度が高く直径も大きいものです。
長さは1フィート(約30cm)や3フィート(約90cm)が一般的で、個人的には3フィートの方が使いやすいと感じますが、当然スペースが必要になります。
密度も様々で、柔らかめのフォームから高密度の固いフォームまであります。
体格の大きなアスリートは高密度、体格の小さい若いアスリートは柔らかめで開始するのが適切です。
基本的な使い方
フォームローラーを初めて使用する場合はとてもシンプルです。
当初は特定の部位に圧をかける指圧的な概念に基づいていました。
フォームローラーを使って筋肉の敏感な部分(トリガーポイント、コリを感じる部分)や、アスリート自身が怪我をしやすいと感じる部分に圧力をかけることが目的でした。
現在では、セルフマッサージ的にふくらはぎ、内転筋、大腿四頭筋といった長い筋肉群にはより長く、より広範囲に圧力を与え、また、大腿筋膜張筋、股関節周辺や中殿筋などの部位には集中的に圧をかける手法が一般的です。
フォームローラーを使う際のポイント
・ローラーの感触や圧の強さは、アスリートの年齢、快適さ、体力レベルに合わせる。
・自分の体重で調整できるため、セルフマッサージでは強度を自分自身でコントロールする。
・いつ、どのくらい行うかの統一基準はないが、一般的には運動前後に使用。運動前は筋緊張を下げウォームアップを促進、運動後は回復を助ける。
・個人的な意見では毎回のワークアウト前に使用、疲労を感じる場合は運動後にも使用を勧めている。
具体的な使用法と部位
フォームローラーは身体のほぼどの部位にも使用できますが、私は下肢で使うのが最も効果的だと考えています。
上半身にはそれほど筋組織の密度が高くなく、アスリートでも上半身の筋緊張は下半身ほど頻繁には起こりません。
ハムストリングスや股関節周辺は筋肉の緊張が最も起こりやすく、私たちはこれらの部位へ重点的にフォームローラーをを用いています。
大臀筋および股関節周辺
利用者はフォームローラーに座り、身体を少し傾けながら骨盤稜から股関節までを動かし、大臀筋をほぐします。
股関節周辺に対しては、対象の脚を交差させて目的の部位を伸長した状態にします。
一般的な目安として、各ポジションでゆっくり10回ローリングします(反復回数などに厳密なルールは設けません)。
多くの場合、利用者の違和感が緩和されるまで動かすように指導します。
大腿筋膜張筋(TFL)および中臀筋
大腿筋膜張筋と中臀筋は小さい筋肉ですが、膝前部の痛みの重要な要因です。
大腿筋膜張筋をケアは、アスリートがうつ伏せになり、ローラーの端を大腿筋膜張筋の上、腸骨稜の少し下に置きます。
大腿筋膜張筋をローリングした後、アスリートは体を90度横向きに回転させ、股関節から腸骨稜までをローリングして中臀筋にアプローチします。
内転筋
内転筋は下肢で最も軽視されがちな部位です。
多くの時間と労力が大腿四頭筋やハムストリングスに費やされ、内転筋にはほとんど注意が払われません。
内転筋をローリングする方法は2つあります。
1つ目はフォームローラーのケアに慣れていないクライアント向けにフロアで行う方法です。
脚を外転させ、ローラーを脚に対して約60度の角度に置きます。
ローリング動作は膝の少し上(内側広筋と鵞足部)から始め、対象部位を3分割して行います。
まず、股関節から膝上までの約3分の1を10回短くローリング。
次に内転筋の中間部分にローラーを移動して再び10回。
最後に、股関節の近く、恥骨結合付近までローラーを置き、最後のセット10回を行います。
2つ目の方法は、1つ目に慣れたアスリートに使用します。
この方法では、トレーニングルームのテーブルやプライオメトリックボックスの上に座り、ローラーに体重をより多くかけ、大内転筋三角をより深く、集中的にローリングします。
その後、一つ目と同じ手順で動作を行います。
上肢への使用
主に下肢に使用しますが、上肢にも使用可能です。
胸筋、広背筋、回旋筋にも同様の手法が使えますが、可動域は小さくなり、動作は指圧に近く部分的に使用する方法になります。
効果の評価
フォームローリングはハードで場合によっては痛みを伴うこともあります。
ストレッチ同様に適切なマッサージやセルフマッサージも不快に感じることがあります。
そのため、クライアントは、トリガーポイントを扱うことによる適度な不快感と、怪我につながる不快感を区別することを学び見分けることが重要です。
フォームローリングを終えたクライアントは、筋肉の症状が悪化することなく、むしろ良くなった感覚があるはずです。
ましてやローラーであざができることがあってはいけません。
各セッション後にアスリートに筋肉の状態を確認し、実施したケアが効果を発揮しているか評価します。
また、私はフォームローリングが効果的かどうか、アスリートの実施状況を観察して判断します。
もし運動前に「ローラーを使え」と言わなくてもアスリートが自発的に使っている場合、技術は効果を発揮していると判断しています。
効果を感じているほとんどのアスリートは自発的にフォームローラーのケアを行うはずです。
フォームローラー vs マッサージ
「どちらが優れているか?」という質問が出ますが、答えは明白です。
手によるマッサージの方が優れています。
手は脳と直接つながっているため、フォームローラーには得られない感覚があります。
もしコストに問題がなければ、常にマッサージセラピストを用意したいところです。
しかし、予算的にそれは難しい場合が多いため安価に導入でき、無制限にセルフマッサージが可能なフォームローラーが便利なのです。
パフォームベターでは長さや形状、仕様の異なるフォームローラーを取り扱っています。ご興味のある方はこちらからご確認ください。
Michael Boyleの寄稿は以上です。
PERFORM BETTER本社ではMichael Boyle以外にも多くの契約トレーナーがいますが、彼らの発信するトレーニングやリハビリ、リカバリーなどの情報がアメリカや世界のスポーツ、フィットネス、医療の現場に活かされています。
次回以降も契約トレーナーからの有益な情報をご紹介させていただきます。
本コラムの内容や紹介した商品について、ご不明点があればこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。
株式会社パフォームベタージャパン