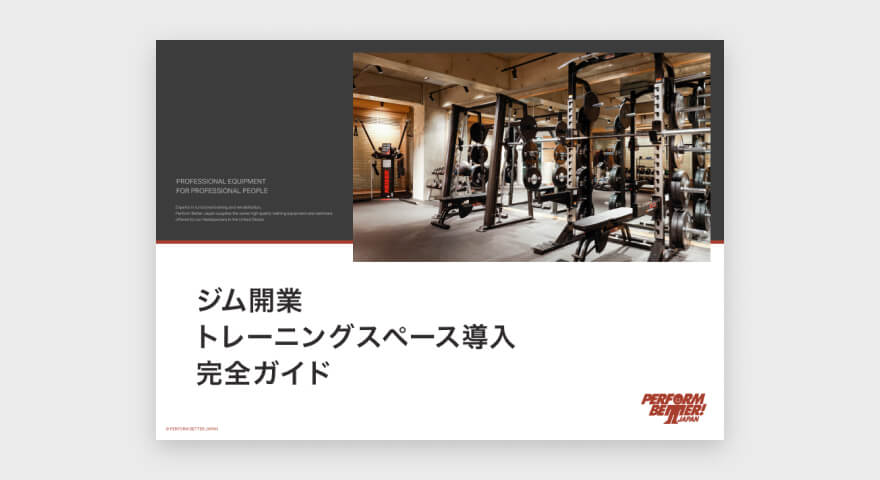今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。
トヨタアスリートスポーツセンターの内田智也先生に「AIを用いたスポーツ動作解析」をテーマに講義いただきました。
本ウェビナーは10/18~19に開催するパフォームベタージャパンサミット2025のプレウェビナーになりますので、ご検討中の方は参考になれば幸いです。
■テーマ:AIを用いたスポーツ動作解析 プレウェビナー編
■開催日:2025年8月28日
■講師:内田 智也 (トヨタアスリートスポーツセンター)
AIを用いた動作解析とは?

近年、AI技術の進歩により、スポーツ動作解析の方法は大きく変化しています。
従来のマーカーを体に貼り付けるモーションキャプチャーは準備や後処理に時間がかかり、研究用途が中心でした。
しかし、AIによる「マーカーレス解析」が登場したことで、カメラ撮影だけで短時間に解析が可能になり、現場での実用性が一気に高まりました。
特に投球動作のような複雑な動きでも、5分程度で解析とフィードバックが行えるようになり、病院やチームの現場でも導入が進んでいます。
動作解析は評価の一部

筋力測定や関節可動域の評価、画像診断などと同様に、動作解析も統合的な評価の一つであり、それ単体で完結するものではありません。
特に重要なのは、数値そのものよりも「どの変数を選び、どのように解釈して伝えるか」。
対象者に合わせたフィードバックが必要であり、プロ選手から学生、一般の方まで、理解度に応じて伝え方を変える工夫が求められます。
リアルタイムフィードバックシステム

トヨタアスリートサポートセンターでは、フォースプレートやジャンプ計測、アイソメトリックスクワットなどを組み合わせ、AI解析と統合した「リアルタイムフィードバックシステム」を構築しています。
たとえば片脚ジャンプや減速動作を評価し、着地時の膝や股関節の使い方を数値化。
さらに直感的に理解できるよう姿勢や体幹の傾きをビジュアルで提示することで、選手自身が動きを修正しやすくなる仕組みを導入しています。
このように「わかりやすいアウトプット」を設計することが、選手の納得感と現場での活用につながっています。
Bridge the gap
AIを用いた動作解析は高精度かつ短時間で可能になりましたが、それを「どう現場に落とし込むか」が大きな課題です。
解析者が提示する変数やフィードバック方法に専門性の偏りが出ると、現場とのギャップが生まれる可能性があります。
その橋渡し役となるのが、指導者やトレーナーです。
選手やコーチの言語と、解析から得られる数値をつなげることが、AI時代の動作解析において欠かせない要素といえます。
Q&A
参加者からの質問に対し、自身の研究をもとに具体的にお答えくださいました。
以下、一部抜粋してご紹介します。
Q1. マーカーとマーカーレスを使い分ける基準はありますか?
A:
屋外や短時間で測定したい場合はマーカーレスが有効です。
一方で、投球動作など上肢の高速運動では精度が落ちやすいため、マーカーを使用した従来型の方法が適しています。
目的や環境に応じて使い分けることが大切です。
Q2. 測定で出た数値とアスリート本人の感覚にズレがあった場合、どのように説明していますか?
A:
数値だけでなく、本人の感覚と照らし合わせて伝えることを重視しています。
怪我予防やパフォーマンス向上といった専門家の視点を背景に、ズレをどう解釈すべきかを明確に提示することで、納得感を持たせています。
Q3. 投球動作をAIで分析する際にボールを誤認識することはありますか?
AIは骨格推定をしているため、ボールそのものを認識していません。
したがって誤認識は基本的に起きませんが、手と足が重なる野球のアンダースローのような特殊な動作では推定が難しい場合があります。
Q4. AIはどのように骨格を推定しているのですか? 精度は実用レベルでしょうか?
機械学習やディープラーニングを用いたアルゴリズムによって関節位置を推定しています。
歩行やジャンプのように手足が明確に分かる動作では高い精度が得られ、実用に耐えます。
ただし、前述の通りアンダースローのように複雑な動作では精度が落ちることもあり、競技や目的に応じた使い分けが必要です。
本ウェビナーは、AIを用いたスポーツ動作解析をテーマに解説いただきました。
サミット本番ではさらに深い内容が展開される予定です。
サミットのご参加もぜひご検討ください。
https://www.performbetter.jp/products/s0098
株式会社パフォームベタージャパン