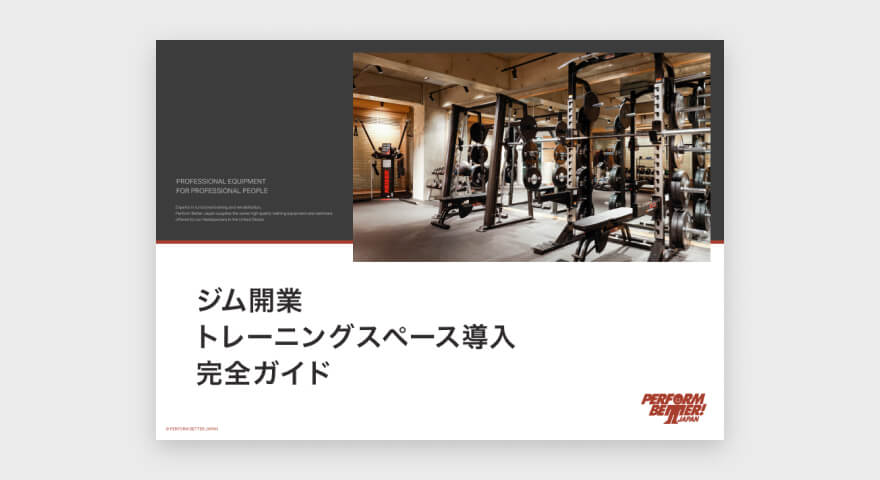今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。
東京大学大学院博士課程で筋肥大の研究を進める加藤光先生に「筋肥大の科学」をテーマに講義いただきました。
本ウェビナーは10/18~19に開催するパフォームベタージャパンサミット2025のプレウェビナーになりますので、ご検討中の方は参考になれば幸いです。
■テーマ:筋肥大の科学 プレウェビナー編
■開催日:2025年8月27日
■講師:加藤 光 (東京大学大学院博士課程)
筋肥大を学ぶ意義

筋肥大には大きく「力学的機能」と「代謝的機能」の2つの意義があります。
力学的には最大筋力の向上や持続的な力発揮能力の向上に結びつき、競技パフォーマンスや傷害予防に寄与します。
代謝的には基礎代謝量の増加や抗炎症性物質の分泌促進など、生活習慣病リスクの低減や健康維持に直結する効果があります。
特に骨格筋は唯一、外的刺激によって量を増やすことができる組織であり、年齢や活動量の低下による代謝不良への対抗手段としても重要です。
現状における筋力トレーニングの課題

これまでの筋力トレーニングの議論は「セット数」「負荷」「種目」といった方法論の組み合わせに偏ってきました。
しかし、個人の経験・年齢・環境・遺伝的要因によって反応は大きく異なり、ガイドライン的な“平均値”だけでは最適解を導くことが困難です。
そのため、現場で重要になるのは「どのような刺激が筋肥大を引き出すか」を理解し、科学的メカニズムに基づいて調整していく視点です。
単一の研究結果に依存するのではなく、研究を統合し、その背後にある生物学・物理学的な原理を踏まえてトレーニングを設計する必要があります。
筋力トレーニングと筋の適応変化の関係(サミットの序論)

筋肥大は「同じ刺激を繰り返せば際限なく進む」ものではなく、一定の適応値に達すると停滞します。
ここで重要になるのは「更新」です。
つまり、負荷の質や量を調整して、新たな適応変化を促すことがトレーニング設計の本質となります。
サミット本番では、この「更新」をどのようにデザインするか、メカニカルストレスや代謝性ストレスといった刺激の質をどう捉えるかが深く解説する予定です。
Q&A
参加者からの質問に対し、自身の研究をもとに具体的にお答えくださいました。
以下、一部抜粋してご紹介します。
Q1. 筋肥大と脂肪燃焼を両立させるために、有酸素運動との組み合わせ方法はありますか?
A:
有酸素運動はエネルギー収支の面で筋肥大にマイナス要素を持つ場合があります。
ただしシステムとして捉えれば、栄養・休養との関係を含めて両立を設計することは可能です。 「仕組み」を理解することで、現場での最適な組み合わせ方を考えられるようになります。
Q2. 刺激を科学的にデザインすることは、理解すれば誰でも現場で活かせますか?
A:
パフォームベタージャパンサミットの講義パートではメカニズムを解説しますが、実技パートでは実際に現場での応用を想定した方法を体験できます。
対象者ごとにどう調整するかも含め、実践的に学べる内容です。
Q3. 年齢が上がると筋肥大は難しくなりますか?
A:
平均的には加齢によって反応性は低下します。
しかし「しにくくなる」だけであり、適切な刺激を与えれば十分な肥大は可能です。
運動内容や方法を年齢に応じて調整することで、効果を引き出すことができます。
本ウェビナーは、筋肥大の科学をテーマに解説いただきました。
サミット本番ではさらに深い内容が展開される予定です。
サミットのご参加もぜひご検討ください。
https://www.performbetter.jp/products/s0098
株式会社パフォームベタージャパン