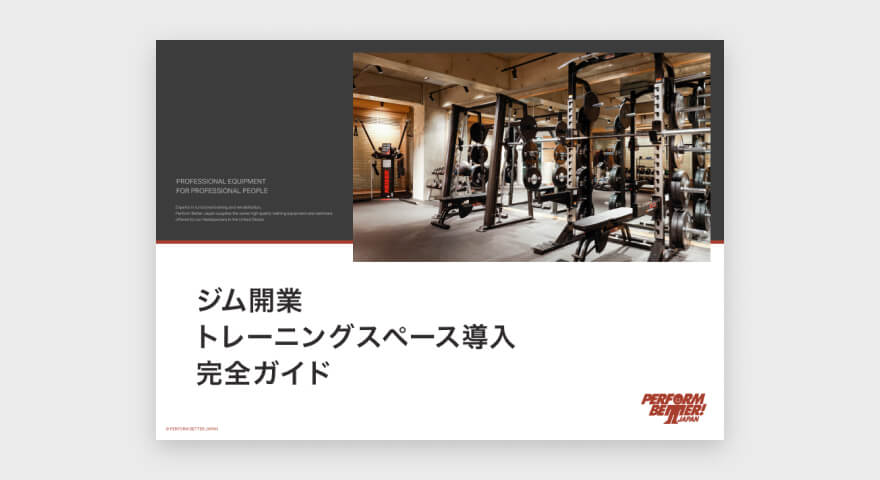今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。
今回のウェビナーでは、日本統合療法株式会社 代表取締役の川合智さんに栄養アドバイスを“栄養療法”へ進化させる」をテーマに解説いただきました。
本ウェビナーは10/18~19に開催するパフォームベタージャパンサミット2025のプレウェビナーになりますのでご検討中の方は参考になれば幸いです。
■テーマ:栄養アドバイスを“栄養療法”へ進化させる - 不調に潜む慢性炎症と低血糖 - プレウェビナー編
■開催日:2025年8月2日
■講師:川合 智 (日本統合療法株式会社 代表取締役)
栄養療法が必要とされる背景:慢性炎症と低血糖の影響

慢性的な体調不良の根本原因として、「炎症」と「血糖調節の不安定さ」が密接に関与しています。
日常的な疲労感や倦怠感、睡眠の質の低下など、病気とまでは言えない不調であっても、炎症マーカーや血糖変動に注目することで、栄養面からの介入が可能となります。
特に慢性炎症は、消化器系、呼吸器系、皮膚、関節など多岐にわたる影響を及ぼす可能性があり、症状が複雑になることも少なくありません。
また、現代の食生活により生じる血糖スパイクや低血糖状態は、自律神経やホルモンバランスを乱し、結果的に免疫機能や回復力を大きく低下させる要因となります。
睡眠障害の裏にある自律神経・ホルモンの乱れ

睡眠の質が低下している背景には、自律神経やホルモン系の機能の乱れが関係している場合があります。
「夜中に目が覚める」「寝つきが悪い」「朝起きられない」といった訴えは、単なる睡眠不足ではなく、低血糖による夜間の覚醒やコルチゾール分泌の異常などが原因となっている可能性があります。
このような睡眠障害に対しては、メラトニンの分泌や副腎機能へのアプローチが効果的とされていますが、栄養の視点からは血糖の安定が特に重要です。
糖質の摂取タイミングや、タンパク質とのバランスを考慮した指導が求められます。
栄養療法を現場で導入する際の考え方
現場で栄養療法を導入する際には、以下の3つの視点が重要です。
1.身体の変化に対する「気づき」を引き出すこと
ただ情報を伝えるのではなく、本人が変化を実感できるような「気づき」を促すことが大切です。
2.過度な制限ではなく、できることから始める方針
完璧な食事管理を求めるのではなく、「今の生活の中で何ができるか」を考え、小さな成功体験を重ねていくことが大切です。
3.エネルギーや栄養素の“底上げ”から始める
多くの方は摂取量や栄養バランスが不足している傾向があります。 そのため、まずはエネルギーや栄養の“底上げ”を意識した介入から始めると効果的です。
これらの視点は、アスリートや医療対象者だけでなく、一般のクライアントにも共通して活用できるアプローチです。
Q&A
参加者からの質問に対し、自身の現場実践をもとに具体的にお答えくださいました。
以下、一部抜粋してご紹介します。
Q1. 料理をしない一人暮らしの方にアドバイスする場合、スーパーのお惣菜やコンビニなどを前提として伝えることもありますか?自炊ではない人への食事指導のケースが多く困っており、コンビニやスーパーでも大丈夫かなと指導しながら少し不安があり、川合さんがどうされているのか知りたいです。
A:
はい、私も実際にそういった方に対応することが多くあります。
調理の習慣がない方や時間が取れない方には、コンビニやスーパーを活用した「現実的な食事の選択肢」を提案することが前提です。
ポイントは、“糖質の質”と“添加物の少なさ”を意識することです。
例えば、脂質が控えめでたんぱく質が摂れる惣菜を選ぶ、サラダチキンや納豆を組み合わせるといった形です。
もちろん理想は自炊ですが、現実的な継続のためには無理なく始められる方法が重要です。
Q2. 川合さんのプロテインを朝ごはんに代替する人が多いです。もし毎朝のプロテインを日課とした場合に日中気をつける点などあれば教えてほしいです。もしくはプロテインは間食程度にした方が良いのでしょうか?
A:
朝にプロテインを摂ることは、胃腸の負担を考えれば一つの良い選択肢です。
ただし、プロテインだけで済ませてしまうと、低血糖状態を引き起こすリスクもあるため注意が必要です。
対策としては、朝に少量でも炭水化物をプラスする、または午前中のどこかで軽く食事を取るなど血糖の安定を意識した補食を入れることです。
また、プロテインを間食にする場合は“足りない栄養素を補う”という意識を持つと、より効果的に使えます。
Q3. 食事療法によりどのくらいの期間で改善していくものでしょうか?
A:
症状や不調の程度によってかなり差がありますが、早い方では2〜3週間で体感の変化を感じることもあります。
ただし、長年積み重ねてきた不調や慢性炎症に関しては、3ヶ月〜半年、あるいは1年単位での継続的なアプローチが必要になることもあります。
改善のスピードは「変える内容」と「変え方」によっても異なりますし、本人がどれだけ実践できるかも重要です。
短期で結果を出すというより、丁寧に継続していくことが大切です。
本ウェビナーは、栄養アドバイスを“栄養療法”へ進化させるをテーマに慢性炎症と低血糖を軸に解説いただきました。
サミット本番ではさらに深い内容が展開される予定です。
サミットのご参加もぜひご検討ください。
株式会社パフォームベタージャパン