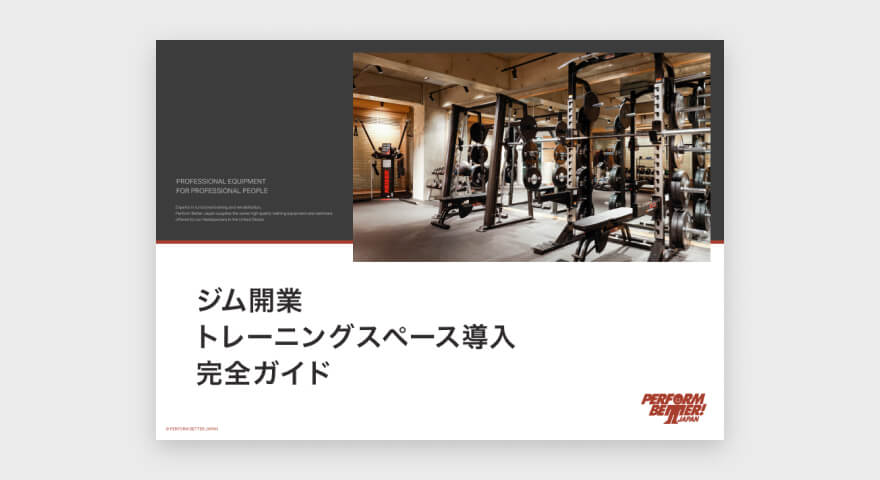今回は、先日開催したFMS JAPAN様とのコラボウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。
FMS/SFMAを現場で導入・活用しているお二人の施設オーナーにご登壇いただき、現場での導入経緯、評価方法、チームでの運用体制など、実際の活用ノウハウを共有していただきました。
■テーマ:パーソナルトレーニングジムへのFMS/SFMAの応用 -FMS/SFMAイントロ -
■開催日:2025年5月24日
■講師
・矢野 耕二 (株式会社One Day Design 代表 / GROUND RULE.代表)
・渡部 真吉 (株式会社e-MOTIONs代表取締役 / Physical Conditioning Lab. Re:Set 代表)
・上松 大輔 (株式会社Functional代表)
FMS/SFMAとは?
FMS(Functional Movement Screen)は、動作のエラーや非対称性を評価し、ケガのリスクを予測・予防するためのスクリーニングツールです。
SFMA(Selective Functional Movement Assessment)は医療領域で用いられる評価モデルで、痛みの原因を構造的に見極める手法として活用されます。
この評価システムは米軍をはじめ、欧州サッカー、MLB、NBAなどのトップアスリートの現場にも導入されており、フィットネスやリハビリ、コンディショニングの領域において世界的に利用が広がっています。
評価の根幹にあるのは、「動作を健康のバイタルサインとみなす」という考え方です。
つまり、単に筋力や可動域を評価するのではなく、「どのように動けるか(ムーブウェル)」を健康状態の指標と捉え、評価・指導・予防介入に活かしていくことを目指します。
FMS/SFMAについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
https://www.functional-inc.co.jp/fms-japan/about-fms-sfma/
活用事例1:GROUND RULE.(矢野 耕二さん)
北九州市で2店舗のパーソナルトレーニングジム「GROUND RULE.」を展開しながら、地域や企業の健康支援にも取り組む矢野さんは、2015年からFMSを導入し、評価に基づく包括的な健康支援を提供されています。
FMS/SFMA導入前は個人の感覚や知識、オリジナルの体力測定をもとに指導していたが、導入後は評価から介入までが体系化され、スタッフ間・医療機関との共通言語としても機能しました。
高齢者や既往歴のある方にも、評価結果に応じた柔軟な適用(例:モディファイドFMS)を行い、安全性を確保しながら個別性の高いトレーニングを実現しました。
「共通言語」「評価から介入までの一貫性」によって、組織的なサービス品質の向上にも寄与しています。
活用事例2:Physical Conditioning Lab. Re:Set(渡部 真吉さん)
秋田県で整骨院、リハビリデイサービス、パーソナルジムを展開する渡部さんは、一般層からアスリートまでを対象に、多角的な評価と個別対応を提供されています。
柔道整復師としての臨床知見を活かし、FMS/SFMAを用いた痛みと動作障害の見極めに強みを持っています。
特徴的なのは、FMSを単なる導入ツールではなく「共通言語」「標準装備」としてスタッフ間で共有している点です。
全クライアントに対して体験時から動作評価を実施し、必要に応じてSFMAやFCSも併用しています。
記録はスプレッドシートとクラウドツールを用いて全てデジタル管理し、フィードバックにも活用されています。
また、パーソナルトレーニングの定義や処方に根拠を求める姿勢が印象的で、「なぜこの種目、この順番、この回数なのか?」に常に答えられるようなプロセス構築を大切にされています。
ディスカッションQ&Aまとめ
Q1. 高齢者にFMSを実施する際のリスク対応について
矢野さんの回答:
高齢者へのFMS実施においては、まず何よりもリスク管理が重要であるとしたうえで、特にモビリティ系(ショルダーや股関節など)の評価は必ず実施しています。
その上で、ロータリースタビリティやトランクスタビリティなどの種目は、実施可能かを実際の歩行動作や会話の中から判断して選別しています。
また、FMSの一部を省略・簡略化して行う「モディファイFMS」も活用し、状況に応じて柔軟に対応しています。
渡部さんの回答:
矢野さんと同様に、モディファイFMSを基本として実施しており、必ずしもすべての種目を実施するわけではないです。
評価を通じて「できない」ということが明らかになった場合、それを元にプランニングするのが本質であり、高齢者であっても健常者であっても、個別の状態に合わせた判断が必要です。
上松さんの回答:
自身の施設では高齢者にFMSを実施する際に、初めからモディファイFMSを行うことはなく、まず通常のFMSを前提にしたうえで、安全性を考慮しながら「できそうにない」ものだけを除外するようにしています。
全体の構成としては、最初にできる限り標準に近い形で評価を行うことを原則しています。
Q2. セミパーソナル形式でのコレクティブエクササイズ提供について
矢野さんの回答:
自身の施設ではセミパーソナルは実施していないものの、過去のチームサポートの経験から、グループトレーニングにおいては対象者の「大枠」で分類したうえで、個々の違いに応じてプログラムの強度や順番を柔軟に変える工夫をしていました。
特に「質と量のバランス」に注意して対応していました。
渡部さんの回答:
スポーツチームの対応経験を踏まえ、あらかじめ1つの種目に対して複数のプログレッションやリグレッションを準備しておくことが重要です。
ラグビーのようにポジションや体格差が大きい場合でも、負荷の調整を前提とする設計を行うことで、セミパーソナルやグループ形式でも対応できます。
上松さんの回答:
チームスポーツの現場で行っていたプログラムを、セミパーソナルの現場に応用していています。
チームでも個人ごとにプログレッションやリグレッションの調整は必要であり、それを前提にセッションを設計しています。
全員に同じ種目を行わせるのではなく、参加者の状態に合わせて内容を最適化していくことが重要です。
Q3. FMS/SFMAの集客・定着への影響について
矢野さんの回答:
FMS自体が集客のツールになることは少ないが、「評価や見立てに基づいた指導をしていること」を啓蒙していくことは必要です。
例えば歯磨きは「道具の使い方は誰でもできるが、磨き方=運動の仕方を指導するのが我々の役割」ですし、その中でFMSのような評価が重要です。
渡部さんの回答:
FMSが直接的な集客に繋がるとは考えておらず、むしろ「質の担保」のための標準装備として活用してます。
クライアントに対して「なぜこのエクササイズを行うのか」を説明できることが専門職として必要であり、そのための物差しとしてFMSを用いています。
上松さんの回答:
自身の施設ではFMSを知って来るお客様はほとんどいないが、「きちんと評価をしてくれるジム」という点に魅力を感じて来店されるケースが多いです。
また、FMSを活用することで「怪我をしなかった」という事実自体が成果であり、定着や継続には貢献していると考えています。
今回はFMS/SFMAの基礎とともに、パーソナルトレーニング施設での具体的な導入例やその意義をご紹介しました。
FMS/SFMAの導入を検討中の方、すでに取り入れているが活用方法に悩んでいる方、またより高いレベルでの個別対応や傷害予防を実現したい指導者の皆様にとって、有益な実践的知見を得られる機会になれば幸いです。
株式会社パフォームベタージャパン