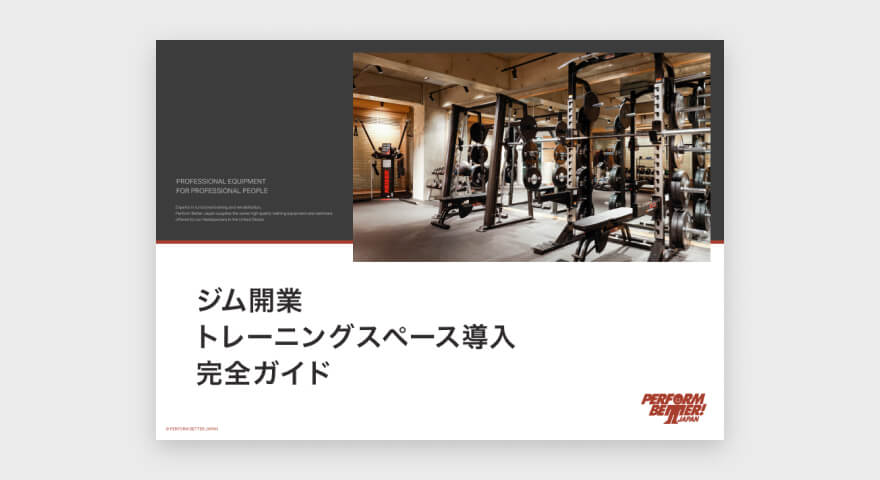トレーニングと野球の技術指導のハイブリッド型パフォーマンスコーチ 木村匠汰さん
Trainer's Journeyと題し、スタートしたシリーズ企画。
この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、それぞれが大切にしている指導の理念や、その考えに至った背景、今後の挑戦について深掘りしていきます。
第5弾は、大阪市住之江区に野球特化型トレーニング施設「BEYOND BASE」を開業し、技術指導とトレーニング指導の両面から野球選手をサポートする木村匠汰さんにお話を伺いました。
指導者志望から野球パフォーマンスコーチへの道

ーまずはこれまでのご経歴と、木村さんがパフォーマンスコーチ(トレーナー)を志したきっかけについて教えてください。
私は小学生の頃から野球をしていて小中学校の頃は北海道の地元のチームでそれなりにプレーにも自信があったのですが、強豪校に進んで高校3年生の時にメンバーから外れてしまったことをキッカケに野球の指導者になりたいと考え、将来は高校野球の監督を目指して教員の道に進もうと思っていました。
実際に教員免許を取得するために大学に進学し、野球部に入るつもりはなかったのですが、入学後に入部することになり、2年生の秋からはキャプテンになったり4年の春までプレーしました。
プレーしていく中で「選手を指導するには身体の仕組みやトレーニングの専門知識も必要だ」と感じ始めて、大学3年生のときに日本トレーニング指導者協会(JATI)の資格を勉強して取得しました。
その学びを通じて、「自分が本当にやりたいことはトレーナーだ」と気づき、指導者(教員)の道ではなくトレーナーを志しました。
大学4年の春に野球部を引退してからは、本格的にトレーナーとしての勉強を開始。
縁あって北海道の札幌国際大学で実績のあるストレングス&コンディショニングコーチの方の元で現場指導しながら学ばせてもらい、その頃にNSCA認定のストレングス&コンディショニングスペシャリスト(CSCS)の資格も取得して本格的にトレーナーの道に進んで行きました。
その後、お世話になったストレングス&コンディショニングコーチからの紹介もあり就職先として選んだのが大阪・堺市にある阪堺病院のトレーニングジムです。
リハビリ施設に併設されたトレーニングジムで、野球の指導に力を入れていたこともあり、「ぜひここで学びたい」と新卒で飛び込みました。
最初は正社員ではなく嘱託のような形からスタートしたのですが、熱意が伝わり正式に雇用していただくことになりました。
阪堺病院SCAでは4年間勤務し、クライアントは小学生から社会人までの野球選手が半分ぐらいでそれ以外はリハビリを終えた一般の方や80〜90代の高齢の方など、本当に幅広い年代・目的の方々を指導させてもらいました。
正直、最初の1〜2年は知らない分野だらけで苦労しましたが、理学療法士やドクターと連携してリハビリ後のトレーニングに関わるなど貴重な経験を積み、そのおかげで視野の広い指導ができるようになったと感じています。
そして野球選手へのサポートにもっと専念したいという思いが強まり、4年勤めた後の26歳の時に職場を退職して筑波大学大学院に進学しました。
大学院では野球の動作やトレーニングについて研究しつつ、並行して野球チームの指導現場にも関わりました。
大学院修了後、大阪へ戻り、現在は自身の施設「BEYOND BASE」でプロ野球選手から小中学生まで幅広い野球選手の指導にあたっています。
科学と伝統を融合する独自の野球指導哲学

ー木村さんは現在、ご自身の施設でトレーニング指導と野球の技術指導の両方を行っているとのことですが、普段の指導ではどのようなアプローチや哲学を大事にされていますか?
施設ではMLBやNPBのトップ選手から小中学生も含めた野球選手のトレーニングから投げる、打つなどの野球の技術指導もしています。
チームに帯同する時は試合中にベンチに入って選手交代や戦術に関わることがありますし、選手の身体データをとって特徴を活かすようなアドバイスをしたりスカウティングのようなことをすることもしています。
指導をする際の大前提は「野球選手のパフォーマンスを向上させる」ことで、BEYOND BASEはそのために作った施設です。
パフォーマンスを向上させるために必要なことを組み立てて提供しています。
具体的には、まずストレッチやコレクティブエクササイズなどで身体機能の改善していきます。
そして次に筋力・パワーを高めるためのウエイトトレーニング。
さらにはオランダの運動学者フラン・ボッシュの理論を参考に、野球のプレーのパフォーマンスに転移する運動学習の要素も取り入れています。
これらを組み合わせて多角的にアプローチすることで、野球のパフォーマンス向上と怪我の予防につなげていくことを心がけています。
ただ、最新の科学に基づくトレーニング理論ばかりを押し付ければ良いわけではありません。
野球界には昔からの指導法や大事にされてきた文化もありますし、現場の監督・コーチが従来の考え方を持っていることも多いです。
私自身、高校野球で伝統的な指導も受けてきましたし、それらを完全に否定するつもりはありません。
特に野球は特殊な面があって自分のパフォーマンスが最大限に発揮できたからといって必ずしも競技結果が良くなるわけではありませんし、実際に結果を出している選手の全員が科学的なトレーニングに取り組んでいるわけでもないです。
なので関わる選手には科学的根拠に基づくトレーニングの意義や考え方のベースとして「こういうものだ」という最新のことを教育しつつ、従来の指導ともうまく折り合いをつけられるよう助言しています。
最新の知見と伝統的なトレーニングの融合
ーご自身も学生時代に選手に経験したことと、トレーナーとして最新のエビデンスを取り入れていく中で葛藤や切り替わっていくきっかけはありましたか?
正直、トレーナーとして学び始めた頃は効率的な動きや代償動作がこうだって指導に取り入れても、逆にパフォーマンスが上がっているかわかりませんでした。
病院勤務の3年目ぐらいから動作パターンや脳や神経などのもっとベースの部分も学び始めたら、全部の正解はわからない中でもある程度の方向性というか、形が見えてきました。
その時点の結論としては結局、伝統的なトレーニングだったり自分自身が学生時代に言われてたことも大事だってことです。
その辺でアプローチもハイブリッドになってきた感じです。
私の感覚としても正直「エビデンスはこうだ」「こういうのが正しい」とこだわってやっていた方が、うまくいかなかった感じはしています。
今ではポテンシャルは高いけど野球につながっていない選手への指導が1番得意だという自負があります。
私自身もベンチプレスやスクワットの重量が上がるだけでは野球のパフォーマンスは向上しなかったですし、野球の練習をいっぱいしても上手くなれなかったのでその悩みを解決できる指導者になりたいなという思いはずっとあります。
技術コーチと信頼を築く対話力
ー技術コーチや選手とのコミュニケーションで意識していることはありますか?また、どのようにして現場から信頼されるようになっていったのでしょうか?
技術コーチの方と話すときにまず意識しているのは、「相手が何を大事にしていて、どんな考えで技術指導をしているのか」をちゃんと聞くことです。
最初に直接お会いした時は必ずその方の考え方やスタンスを伺って、「これは言ってもよさそう」「これは控えた方がいいな」といった情報を自分の中で一度整理します。
その上で、「今、チームとして改善したいことって何かありますか?」と先に聞くようにしています。
そうすると、「あの選手がこういう状態で」とか「このバッティングが気になるんだよね」といった話が出てくるので、そこから少しずつ「だったらこういうアプローチもあるかもしれませんね」と、対話を通じて自然にこちらの提案を入れていくようにしてるんです。
いきなり「これが正解です」みたいな言い方をするとやっぱり壁ができてしまうので、あくまで“対話ベース”で進めていくことが重要だと感じています。
これは特に、新しく関わるチームや初対面の指導者の方と接する際には、すごく気をつけているところです。
自分が大学院で得た知識や理論をベースにしたとしても、いきなり科学やエビデンスを押し付けてしまうと、技術系のコーチから警戒されてしまう場面は正直まだまだ多いので。実際、うまく対話にならないケースもあります。でもそういうときに、「それは僕に任せてもらって大丈夫です」と現場で信頼を得て任せてもらえるような立場になれることが、トレーナーとしての目標でもあります。
また、選手との関係でも同じで、自分の考えを押しつけず、選手がどう感じているかをよく聞いて、そこに自分の知識や提案をうまく“重ねる”ようなコミュニケーションを心がけています。
現場で「信頼されるパフォーマンスコーチ」になるには、知識や技術と同じぐらい、コミュニケーション能力が求められるなと実感しています。
野球界からも認められ始めたきっかけ
ー何か具体的に認められ始めたことを実感したきっかけはありますか?
信頼を得てたと実感した一つ目の転機は、大学を卒業した1年目から国立の和歌山大学野球部に関わっていて、数年かけてチームが安定的に結果を出して今では優勝して全国大会に出るようなチームになっています。
必ずしも高校野球で活躍した選手ばかりではないメンバーのパフォーマンスが上がり、チームとしての結果も出ていく過程で、「木村が関わってチームが強くなった」と野球界の中で徐々に認知されていったんです。
そこから少しずつ、自分のトレーニングや考え方が周囲に認められるようになっていったという実感は初めてありましたね。
その後、大学院に入ってから筑波大学の野球部にも指導させてもらう機会があって、その時にレギュラーではない選手がレギュラーになり、首位打者を獲り、最終的には日本代表合宿に呼ばれるようになりました。
その頃に私もSNSなどで自分からも情報発信を積極的にしていてフォロワーも増えてきて実感が増していきました。
更にそこからMLBの松井裕樹選手からお声がけ頂いたりプロ選手の指導にも携わるようになったので三段階で認めていただけていることを実感していきました。
大学院、SNS、往復生活…過酷な2年間
ーここまで順調にキャリアを積んできたように見えますが、振り返って「これは大変だった」「苦労した」という出来事はありますか?また、それをどのように乗り越えましたか?
最も大変だったのは、筑波大学大学院で過ごした2年間です。
26歳で勤めていた病院を辞めて入学したわけですが、「大学院生」という立場だけに甘んじず、同時に指導者としての現場経験も積もうと決めていました。
そこで当時、週の半分は関東の筑波で授業や研究、残りの半分は関西で野球チームや選手の指導をするという生活を2年間続けたんです。
平日は筑波で研究に打ち込み、週末は大阪に戻って指導――まさに東奔西走の日々でした。
研究では野球の動作解析など専門的な課題にも追われ、時には深夜まで分析作業をしてそのまま車で羽田空港へ向かい、早朝の便で伊丹空港に飛んで機内で睡眠をとり、着陸したら大学のグラウンドに直行なんてこともありましたね。
肉体的にもハードでしたが、自分を鍛える意味では非常に濃密な2年間でした。
また、この大学院時代に合わせて、自分の名前を野球界に広く知ってもらうための発信にも力を入れ始めました。
具体的には先述したSNSでの情報発信をスタートし、さらに野球選手向けのオンラインサロン(コミュニティ)も立ち上げました。
ちょうどコロナ禍で指導現場が制限される中、Zoomを使ったオンライン指導や情報交換が盛んになり始めた時期で、野球界ではオンラインサロンは珍しかったのですが、その先駆けとして挑戦したんです。
同時に複数のチャレンジを抱えて正直しんどい部分もありましたが、結果的に大学院での研究で理論的土台を築け、SNSやオンライン活動で野球界に名を知ってもらう基盤を作ることができました。
この過酷な2年間を乗り越えたことで、自分の指導者としての方向性が定まり、大きな自信にもつながったと感じています。
セミナーから海外視察まで、貪欲に学びを追求

ー常に最新の知識や技術を取り入れて指導されている印象ですが、ご自身のスキルアップのために日頃から心がけている学びの習慣はありますか?
まず、指導者としてアップデートを続けるために、基本的に毎月何かしらのセミナーや研修会に参加するようにしています。
最近では「AZCARE ACADEMY」というトレーナー向けのアカデミーにも入学しましたし、他にもパフォームベタージャパンさんのセミナーでよく名前を聞く方々のセミナーにもよく参加しています。
月に一度は新しい知見をインプットし、自分の指導内容をブラッシュアップして精度を高めていく。
そういった自己研鑽を欠かさずに続けています。
さらに、自分の視野を広げるために海外にも目を向けています。
大学院を修了した2年ほど前には、時間を作ってアメリカの野球トレーニング施設を視察しに行きました。
BEYOND BASEを作るつもりだったので、メジャーリーガーを多く指導されていて私が最も尊敬しているエリック・クレッシー氏の施設にも実際に赴き、MLBの世界ではどんなトレーニングが行われているのか、施設の仕組みやトレーニングコーチ、バッティング、ピッチングコーチがどのように協業していて、指導体制はどうなっているのかを肌で感じました。
初めての海外渡航だったのですが、本場の空気に触れて「さすがアメリカは環境が整っている」と刺激を受ける一方で、指導内容自体は「日本も負けていないな」「すでに入ってきているな」と思う部分も多かったですね。
むしろ日本の方がきめ細かい指導ができている点もあると感じ、世界基準を知ったことで自国の強みを再認識できました。
この経験によって、自分が進めている指導の方向性に自信を持てましたし、良いところは積極的に取り入れようという貪欲さも一段と増したように思います。
全国展開と中高年・ジュニア世代への新たな野望

ー最後に、今後の目標やビジョンについて教えてください。木村さんは将来どのような指導者になりたいとお考えですか?また、新たにチャレンジしてみたいことがあればぜひ伺いたいです。
今描いている一番大きなビジョンは、現在大阪にある「BEYOND BASE」のような野球特化のトレーニング施設を全国に展開していくことです。
このBEYOND BASEは「野球選手の人生を変えていく場所」をコンセプトに掲げてスタートしましたが、同じような環境を日本中に増やして施設の施設の価値や取り組みを最大化させていきたいと思います。
各地にそうした拠点ができれば、指導者(トレーナー、パフォーマンスコーチ)にとっても活躍の場が広がりますし、必然的に選手にとっても身近なところでパフォーマンスを伸ばせるチャンスが増えると思っています。
トレーナー個人としては、今指導している選手たちを一人でも多く野球のパフォーマンスを向上させて、その選手を長く活躍させることが使命だと思っています。
将来的には、自分が育成に関わった選手からNPBやMLBで活躍するスター選手が生まれたり、現在指導中のプロ選手がより高いレベルで成果を出せるような指導をしていきたいと考えています。
また、いずれは自分自身が野球チームを持つことにもチャレンジしてみたいです。
実は2025年5月からジュニア向けのトレーニングプログラムを本格的に始動する予定で、ゆくゆくは小中学生年代のチームを作り指導から強化まで一貫して手がける構想もあります。
さらに将来的には企業と提携して社会人のクラブチームを設立し、私の施設で育った選手がそこでプレーしながら働けるような仕組みづくりもできたら面白いかなと考えています。
野球をやりたい人が思い切り取り組める環境を整え、日本の野球界に新しい価値を提供していくことが今後の目標です。
木村匠汰 プロフィール:経歴と現在の活動
木村 匠汰(きむら しょうた)
1994年生まれ、北海道出身。高校まで野球一筋で、指導者を志して札幌国際大学に進学し教員免許を取得。在学中にトレーナー資格を取得しトレーナーに転向。大学卒業後は大阪・阪堺病院SCAでトレーニング指導者として4年間勤務。筑波大学大学院修了。2023年、大阪市住之江区に野球特化型トレーニング施設「BEYOND BASE」を開設。MLB・NPBのプロから小中学生まで指導する野球パフォーマンスコーチ。