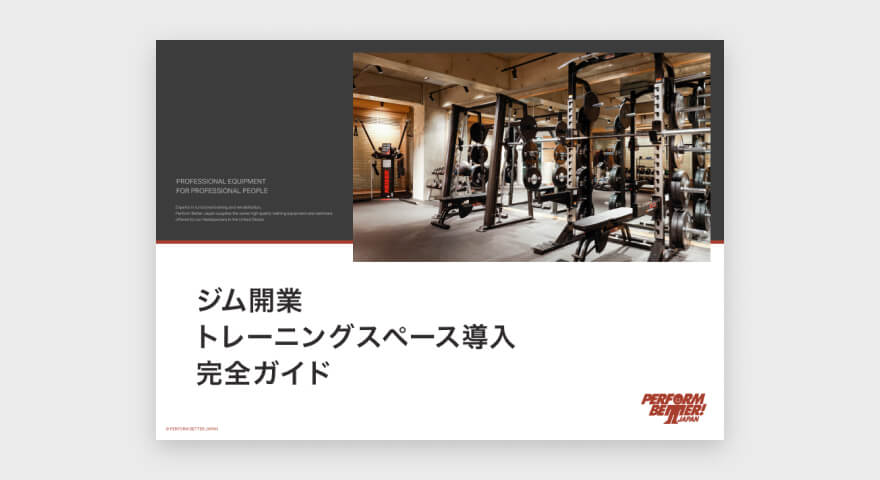Trainer's Journeyと題し、新たにスタートしたシリーズ企画。
この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、ご自身の指導で大切にしていることや、そのように考えるようになったきっかけ、今後挑戦したいことなどを深掘りしていきます。
第二弾は、パーソナルトレーニング、介護事業、お風呂屋さんなど幅広く事業を展開している有限会社新井湯 P2M GroupのGMとして活動されている新井 颯太(あらい そうた)さんにお話をお伺いしました。
|父の誘いでフィットネス業界へ
ーこれまでの経歴と現在のお仕事について簡単に教えてください。
東海大相模高校で野球をしていたこともあり、卒業後は東海大学体育学部のスポーツ&レジャーマネジメント学科に進学しました。
当時は、将来スポーツ関連の職種につこうという思いはなかったため、あえて体育学部らしくない学科を選び、遊園地やテーマパーク、スポーツイベントの運営・マネジメントなどについて学んでいました。
そして私が大学2,3年生ぐらいの頃に、父の誘いで現在勤務している有限会社新井湯のアルバイトとして働き始め、現在はその中のP2Mというフィットネス事業のグループでGMを務めています。
そのほか、自社のアカデミー活動やフランボッシュ公認のセミナー「STC:Strength Training and Coordination」を日本ホストとして運営しています。
ーご実家の有限会社新井湯さんで働くことになった経緯について詳しく教えてください。
私の父が代表を務めている有限会社新井湯は1952年にお風呂屋さんから始まっている会社で、私が小中学生ぐらいだった2003年に介護事業がスタートしました。
その後、コロナが流行り始める少し前にフィットネス事業部を立ち上げることに。当時の私は全く会社には関わってなかったんですけど、立ち上げスタッフが足りないという理由から父に誘われ、1店舗目のオープンのタイミングでアルバイトスタッフとしてフィットネス事業に関わり始めました。
その時もトレーナーをやろうと思ったわけでもないですし、「人が足りないなら受付スタッフとして手伝うぐらいならいいかな?」という気持ちで働き始めました。

|大学生で経験した、ジムの立ち上げ責任者
ー受付のアルバイトからトレーナーに転身したキッカケは何だったのでしょうか?
P2Mグループの1店舗目のジムは40歳以上にフォーカスした施設だったんですが、最初はそこで受付スタッフの業務だけをしていました。
その後、その施設で夕方に開催していた小中学生向けの運動教室の指導をしてくれないか?と父に相談されて担当することになったのがキッカケです。
トレーナーの勉強はしていなかったので全く分からないところからのスタートだったんですけど、とりあえず他のトレーナーが作ったメニューの通り進めてほしいと言われて、受付のアルバイトを始めたのと同様に自分の意思だけではなく誘われる感じでトレーナーとしてのキャリアが始まりました。
運動教室の指導を始めてみると、「せっかくやるんだったらしっかりと突き詰めて目の前にいる子供たちへより良いサービスを届ける方法はないかな?」と思い始めて、その頃からトレーナーとしての業務や運動指導に関わる勉強にもスイッチが入りました。
ーそこから今のように事業を展開していくキッカケや苦労されたことを教えてください。
最初は受付と子供たちの指導だけを任されていたのですが、たまたま近くに空き物件ができて、そこで子供の運動教室に特化した施設を作ることになりました。
大学の同級生と2人で受付スタッフをやっていたのですが、代表から「これぐらいの金額を出してあげるから、学生二人でやってみるだけやってみるか?」と話をいただき、全くトレーナーの経験のない2人がジュニア専門のジムを立ち上げることに。
施設を作っていく過程では、施設の準備ももちろん大変だったんですけど、それ以上に仲間集め、それからその仲間たちとのコミュニケーション、チームビルディングに非常に苦悩した記憶があります。


ー大学生でありながらジム立ち上げの責任者を任されるというのはかなりのプレッシャーですね。立ち上げ当時に苦労したことやそこからの学びはありますか?
そうですね、正直な話をするとジュニア専門ジムの立ち上げ初期メンバーとしてなんとか5人ほど集めたものの、今現在残っているスタッフは誰一人いないんです。
当時のメンバーが全員辞めてしまったというのが僕の苦い経験です。
スタッフがなぜこうもやめてしまうのか、その当時の僕には全く理解できませんでした。
ただ、なぜかやめていってしまうという現実に直面して、理由に思いを巡らせる中で「原因は自分にあった」と心の底から思いました。
自分がもっとスタッフが働きやすい環境を作り、それぞれの強みが生かせるような役割分担を行っていれば…。もっと目指すべき方向を指し示し、スタッフとのコミュニケーションを円滑にできていれば…と反省し、このことをきっかけによりよい組織作りを目指すようになりました。
それからは、様々な経営者の方のお話を聞いたり、いわゆるリーダーと言われるような方々の書籍を読んだり動画を見たりして、チームを作る上での重要なポイントを掴んでいきました。
その中から「ここは外してないよね」という共通項を見出し、自分たちらしい組織作りに取り組んできました。
ー苦い経験を経て “自分たちらしい組織作り”を行ううえで、上手くいった事例や大事にしている考えがあれば教えてください。
3つあるのですが、まずは「とにかくコミュニケーション量を増やすこと」を意識しました。
初期はみんな学生だったのですが、ちょうどコロナの影響で授業がオンラインだったので基本的には全員が毎日施設にいるような状況だったことも幸いしました。
2つ目は「スタッフ一人一人が成長できる環境」を必死に作りました。
1年、2年と長く勤めていく先にどんな自分が待ってるのか、この会社にいたら成長を実感できる、未来の自分にわくわくできる、そんな風に感じてもらえる職場を目指しました。
具体的には、月に数回は新たな知識を得るための研修会を必ず開催したり、トレーニングセッションの合間に業務内容の事細かな確認をしたりと、スタッフの学びに対する欲に応えられる環境作りに力を入れました。スタッフの興味関心や前のめりな姿勢にもとても感謝しています。
最後に「自分たちの組織の目指すべき方向を指し示すこと」です。
これがとても大変だったのですが、本当にやって良かったし、今もそれがない状態は無しにしようと思っています。
やっぱりこの組織がどこに向かって進んでるのかわからない状態では、メンバーやアルバイトの学生達にも「一緒に働こう」とは言えないですし。
自分たちがどんな目的でこういうサービスを提供しているとか、どんな目的でこの現場に立ってるのかっていうところを常に確認できるようにしています。
たとえば、一番星を見ると、星ってすぐにわかると思うんですけど、そこにたどり着けるかというと、たどり着けないかもしれない、でも星を見ると、あそこまで行ってみたいなって思える。そんな風にみんなが向いている方向がいつでも分かる組織にしたいなと思っています。
ただ、逆に近すぎる目標もよくないと思っていて。たとえば東京タワーの上なんかだと少し頑張れば手が届いてしまいそうですよね。
組織としてはもっと上の目標を設定した方が良いと思っています。
そのうえで、経営者が組織として目指すべき“一番星”を作り、スタッフの鼓舞につながるような夢を語ってみせる。
どうなるかわかんないけど、そこに向かって全力で一緒に走ってみない?と当時の学生達に問いかけ、だから一緒に働こうっていう話をしていました。
|2歳児から101歳まで。地域の方すべてがクライアント
ー普段のトレーニング指導についてもお聞かせください。
有難いことに毎日幅広い年齢層の方々のトレーニングを担当させていただいています。
昨日もイベントで2,3歳の子供達を現場で指導していたのですが、小さなお子様を相手にグループ指導を行うことも多いです。
スケジュールは日によって違いますが、1日中セッションを担当する日は午前中に介護事業で高齢者の方に運動指導、夕方は小中学生に向けてスポーツが上手くなるためにはこんな体が必要だよっていうような指導して、18時頃からは高校生や大学生、社会人アスリートに対してパフォーマンスアップのための指導も行なっています。
そのほかの時間には、主婦やビジネスマン、ご高齢の方々のトレーニングを担当しています。
ーまさに地域の方々全てがクライアントですね。
はい、おっしゃる通りです。品川区から介護予防事業の委託を受けていて、65歳以上の方々への運動教室の指導員として現場に立つことももちろんあります。
P2M Performance という普段はアスリートを見る施設では、午前中に機能訓練特化型のデイサービスもやってるので、そこの介護職員として運動指導も行なっています。先日は101歳の方がいらっしゃいました。
ーこれだけ広い年齢層の方を指導するのは大変だと思うのですが、なぜこのような体制になったのですか?
先ほどお話しした通り、有限会社新井湯では介護事業、子供の運動教室、40歳以上向けのフィットネスといったように、対象者別に施設を分けてサービスを提供していました。
ただ、まれに介護予防の現場に出たり、70代や80代の方にパーソナルトレーニングを提供する機会がありました。
その中で「トレーニングシステムや根本的な理念の部分は共通しており、同じようにサービスを提供できるのでは?」と感じたのがきっかけです。
その思いの具現化と店舗展開の集大成として、どの世代に対しても同一施設でP2Mグループの理念やトレーニングシステムにもとづくサービスを提供できる場所を作りたいという思いから、P2M Performanceを出店しました。
それから、地域の皆様にサービスを提供するうえで、対応できない人たちを作りたくないという思いもありました。
よく代表とも「あったら街の人が喜ぶ施設」を作りたいよねって話をしていて、自分たちが提供したいサービスを届けるわけではなく、どんなサービスでも求めている人はいると思うので自分たちのこだわりというより街の人たちが喜ぶこと、この街に住む全ての世代が少しでも「いいな」って気持ちになれる場所を作っていきたいと思っています。

|インプットの根底は自分と組織のため
ートレーナーとしての業務で1日中忙しいと思いますが、ご自身の時間はどう確保されていますか?
先ほど例に挙げた1日はトレーナー業が多い場合のスケジュールなのですが、マネージャー業務として店舗のミーティングだったり、講習会の資料や動画、チラシを作ったりと結構やることが多いのでプライベートの時間は今はあまりないかもしれません。
ー新しい知識や情報をインプットする時間を確保するのも難しそうですね。
そうですね、僕はインプットのための時間を確保というのは意識的には行なっていないです。
そういうと少し語弊がありますが、気になったことや学びたいことがあれば際限なく今できることをやるって感じです。
多分みなさん生活しているとそうかもしれませんが、仕事のことは常に頭の中にあって、何かオンとかオフとかを自分の中では全く決めずに常にどちらでもある状態です。もちろんそれを推奨しているわけではありませんが(笑)
僕にとってのインプットはすべて誰かに伝えたり、何かに生かすことが目的。
たとえばスタッフへの研修するためのインプットなんかがいい例です。
基本的にはなんらかの壁にぶち当たって、その課題をクリアするために必要だから随時インプットするという流れで進めています。
ー新しい情報を取る手段は何が多いですか
使えるものはひたすら全部使うっていう感じです。
書籍だけでは正直理解が追いつかず、その人の言葉を聞きたいって思ったら、現地に赴いてセミナーに参加させていただくこともありますし、オンラインで動画を視聴することもありますし。
あとは職場の仲間から教えてもらうこともあります。
学びのコンテンツは数えきれないほどあるので、特に何かこれっていうこだわりはないです。
ーインプットする情報を選ぶときの基準はありますか?
「自分が必要と感じたか」あとは「仲間がそれを求めてるか」ですね。
今の組織に欠けていることや仲間がこういうことで困っていて解決する術が他のスタッフにもない、といった時は積極的に学ぶようにしています。
自分に知識を蓄えようみたいな感覚とは違って、これをどういう風に組織の財産として形成していけるのかなっていう視点を持ちながらインプットしています。
これをどうやってわかりやすく仲間に説明しようとか、このお客さんに使えるんじゃないか、など最終的な目的を考えながらインプットすると、自然と情報も整理されていきます。
繰り返しになりますが、地に足のついた活動にするため、何より組織づくりに力を注いでいますので、自身がインプットしたものは常に組織に還元することを意識しています。
ートレーナー活動を始められたばかりの頃と現在とでインプットの方法に変化はありますか?
そんなに変化はないですが、視野や少し拡がったかもしれません。
子供向けの運動指導を始めた頃にパフォームベタージャパンサミットに参加してそこで視野が一気に拡がりました。
そこで出会った講師の方々が個別で開催されているセミナーにも足を運び、たくさん学ばせていただきました。
ーサミットがお役に立ててよかったです。パフォームベタージャパンサミットに参加したキッカケはなんだったんですか?
当時、私が中学生のときにお世話になっていたトレーナーさんのところに勉強のために通っていたんですが、その方がCFSCっていうマイクボイルが発行しているS&Cの資格のマスターコーチで。
それでマイクボイルの施設のSNSを見たり器具を調べていたらアメリカのPERFORM BETTERさんを見つけて、日本法人があることが分かりサミット開催の情報を見つけました。
「面白そうだから行ってみようと思っている」と相談したところ、そのトレーナーさんもすすめてくださったので参加しました。
|STCコースの日本展開

—STCコースの日本ホストも行われていますがキッカケについて教えてください。
実は、STCの講習会を日本でやりたい!って強い思いがあったわけではなかったんです(笑)
私がフランボッシュの理論に触れたのは、2019年のパフォーマージャパンサミットです。
そこで講師の方々がその理論のお話をされていて興味を持ち、個別の講習会に参加したり書籍を買って読んだりするうちに本質をついている理論だなとさらに興味が高まりました。
当時のクライアントは運動教室に通う小中学生だったので、その理論を活用したアプローチを子どもたちに届けるために学んでいたのですが、自分の学びや実践内容ををアウトプットする目的でInstagramにエクササイズ動画などを投稿していました。
すると、たまたま韓国でSTCコースの講習会を主催している教授が僕のInstagramの投稿を見てくださっていたみたいで「こういう講習会を韓国でやっているので、一度見に来てください」とDMでメッセージをいただき、韓国に行って講習会に参加させていただきました。
内容は僕が本でずっと読んいたことだったんですけど、それを実際に体験したらこれはめちゃくちゃ面白いし魅力的なコースだなっていうのが正直な感想で。これを日本で普及するために何か力になれたら嬉しいですと、その場で教授にお伝えし、2023年の5月に初めてSTCジャパンとしてコースを開催しました。
STCコースをはじめとしたセミナー活動をおこなうことで地域の皆様以外にも、スポーツをする子どもたちや、アスリート、そして参加されるトレーナーの皆様を通して、全国にP2Mグループが大事にするトレーニング、コンディショニングの考え方を発信できればと考えています。
|今後の目指す姿
—憧れのトレーナー像はありますか?
大前提として、私自身本当に色々な方々から学ばせていただいているので、その皆さんを心の底から尊敬してるんですけど、トレーニング指導についてあり得ないほどこだわりがあるかって言われるとそうでもないんです。
だから「憧れのトレーナー像」と言われると難しいですね。
ただ、目の前の方を幸せにする手段として今まさに色々なことを学ばせていただき、本当に多くの方とのご縁でトレーナーという仕事に就けているので、自分が今できる最大限のことをして誰かを元気にしたり幸せにしたり感動させられたらなと思っています。
なので、自分にとっての憧れの対象はトレーナーっていう括りではないのかなと思っています。
ーチャレンジしていることはありますか?
P2Mグループは地域密着で5店舗を構えさせていただいて、全ての世代に対して笑顔を届けたり、幸せや感動を届けて、最終的にはいろんな方々にとって「拠り所がある街」を作ってみたいなと思っています。
僕らはトレーナーなので、どうしても身体の機能の面にすごく目が行きがち。
この方の体の機能を改善してあげようとか、この方の望み通りの身体にしようとかそういうことを考えがちだと思うんですけど、トレーナーが持っている可能性ってそこだけではないかなと思っているんです。
もちろん知識をつけてアプローチの幅を広げることで、運動や栄養、休養のソリューションを届けていくっていうことも一つ大切なことだと思います。
ただ、それは“身体に限った話”であって、心理面や社会面においてもトレーナーととして何か別のアプローチが見つかってもいいのかなって常に思っているんですね。
たとえばちょっと極端な話ですけど、トレーニングの知識が全くないトレーナーでも、色々な方法で目の前の人を笑顔にすることって多分できると思うんですよ。
その笑顔になった方が、健康か健康じゃないですかって言ったときに、それは健康だといえると思うんです。
笑顔じゃなかった方が笑顔になったとか、何か不安を抱えていた方が少し安心できたとか、それも僕らにとっては健康のあり方の1つでパフォーマンスアップだと定義しています。
こういう心理面や社会面に対して、街の中で何かいろんな事業やサービスを展開したり、イベントを開催したり、運動指導で身体を変える以外で何かもたらせる価値はないかなと、常日頃追求しながら活動しています。
なので、とにかく身体のことを学んで身体に対するアプローチだけじゃなくて、他にもっと僕たちが1人の人間として目の前の人に何かを届けられる可能性はないのかなっていつも考えながらチャレンジしています。
ーインタビューへご協力いただきありがとうございました。
|プロフィール

新井 颯太(あらい そうた) 26歳
父親が代表を務める株式会社新井湯のフィットネス事業部立ち上げをきっかけに、トレーナーとしてのキャリアをスタート。大学在学中にジュニア向けの運動教室の立ち上げ責任者を経験。現在は、株式会社新井湯内のP2M GroupのGMを務める傍ら、自らもP2M Performaneのトレーナーとして子どもから高齢者まで広く指導を行っている。また、フランボッシュ公認のセミナー「STC:Strength Training and Coordination」を日本ホストとして運営している。